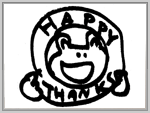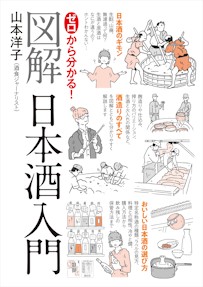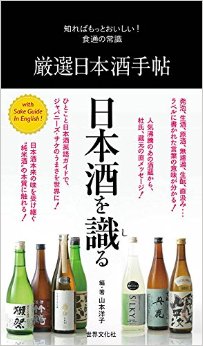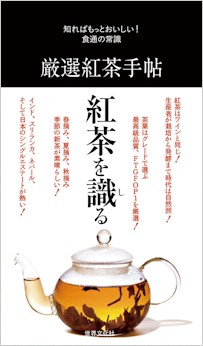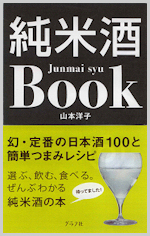ご当地もの
« Previous Entries Next Entries »秋田三大発酵食で酒の肴
May 24, 2011というわけで、発酵食品の生産者さんを3カ所訪問したのでした
それがいかに秋田の日本酒にあうか、番組でお伝えしたのです。
いぶりがっこの高橋朝子さんのいぶりがっこ。もちろんそのままでもおいしいですが、上等のオリーブオイルをたら〜りかけると、不思議と卵黄のようなコクが。そこに、ベジタリアンのキャビア、ぷちぷちの食感が楽しい”とんぶり”をパラリ。粗挽きの黒こしょうパラパラリで辛みもプラス!するとベリーお酒向きの一品に。
『いぶりがっこのカルパッチョ風』
材料
いぶりがっこ 適宜
エキストラ・バージン・オリーブオイル
トッピング=とんぶり、黒こしょう
作り方
いぶりがっこを薄くスライスする。皿に並べ、EXVオイルをかけ、トッピングをふる。
それから
桧山納豆!
白神大豆を丁寧に蒸したコクある味。十四代目に教わった秘伝タテマゼで、ふんわり上下混ぜ混ぜ。おすすめは「塩」
コシあります。
温かい玄米ごはんにかけると最高です!
もちろんお酒のつまみにもグーッ!
諸井醸造所のしょっつるを醤油の代わりに入れると深みがゴツンと出てよかったです。それをオムレツにするとよりおおつまみ向き! 火を通しすぎない半熟でどうぞ。ネギもたっぷりがいい感じ!
しょっつる納豆のオムレツ↑
しょっつる+納豆に、いぶりがっこを合体させると最強でした!
『しょっつる納豆いぶりがっこ』
材料
納豆90g
しょっつる 小さじ1
いぶりがっこ 2cmくらい(細かく刻む)
細ネギ 1本(細かく刻む)
作り方
納豆を混ぜ、粘りがでたら、いぶりがっこ、しょっつる、ネギを加えてよく混ぜる。まずは、そのままで! そこからアレンジも楽しいです。
例えば
●アレンジその1 卵1個加えて混ぜ、そのまま食べる。
その1の2 フライパンで焼いてオムレツにする。 炒り卵風にしてもよい。
●アレンジその2 油揚げに入れて焼き、稲荷風に。
●アレンジその3 厚揚げか水切りした木綿豆腐にのせて焼いて田楽風に。
「混ぜる時は、タテマゼでぜひ!」
そして!
『いぶりがっこと大根の親子サラダ』
いぶりがっこ、大根、しょっつる、ごま油……適宜
いぶりがっこと大根をせん切りにする。しょっつるとごま油を1:1で混ぜ合わせたドレッシングであえる。好みでカイワレ大根をのせる。
発酵食品は実に柔軟で奥が深いです!
飲みたくなってきました〜
しょっつる諸井醸造所その2
May 24, 2011超長期熟成した桶を見ると、表面がチョコレートのよう。
表面をはらうと、中からペースト状になった熟成ハタハタが、搾る前のしょっつるです。「しょっつるペースト」ですね。
ひとさじもらっていただいたらうまみのカタマリ!
原料はハタハタと塩のみ。それが発酵という微生物の力で、うまみがカタマリ化するのです。すごいっ。
そして濾過を丁寧にしっかり。だから澄んだ味に。
そんなハタハタしょっつるだから、豆腐やカマンベールチーズにかけると、それだけで美味なる酒のつまみに様変わり。カマンベールチーズとしょっつるのジョインはぜひお試しください。純米の冷やからお燗向きです! 旨味が強いので、材料も調理も超シンプルでおいしい一品に。
例えば ↓
超シンプル!「しょっつるスープ」
純米酒を加えてぐっと美味しくマイルドに。お酒がすすむ温かなお吸い物。お酒を飲む前、飲む途中、飲んだあとにも良いですよ〜。
材料
しょっつる 小さじ1
水 180ml
純米酒 20ml
作り方
材料全部を鍋に入れ、沸騰させる。器に注ぎ、 粗挽き黒胡椒を少々ふる。
*お好みでネギやセリ、クレソンなど薬味野菜、夏なら小さくカットしたきゅうりのサイコロ切りなどを入れてください。アレンジ自由自在。
____________________
●しょっつるの旨味が豆腐の甘みと抜群の相性 クリーミィな食感が楽しい!
「しょっつるくずし豆腐」
材料
豆腐1丁
しょっつる 小さじ1
にんにくすりおろし 少々
好みで黒胡椒 (or 七味 or 山椒)
作り方
フライパンに豆腐を入れ、水気をとばす。 しょっつるをまわしかけ、にんにくを入れ、水分が飛ぶまでじっく〜りと炒める。器に盛り、黒胡椒(または七味、または山椒)、ネギをトッピングしても。 超簡単で美味!
*豆腐はできるだけおいしい、いいものでお試しください。自然食品店などで高い豆腐が賞味期限間近で安くなっていたらチャンス。豆腐は冷凍できるので安い時に冷凍しておくと便利です。その場合は自然解凍で。
諸井秀樹さんと。手に持っているのは諸井醸造所のスタンダード・秋田しょっつるハタハタ100%、そしてしょっつる十年熟仙です。
●十年熟仙
10年モノのビンテージしょっつる!
「通常商品の3年熟成より、更に倍以上の10年間もの時間をかけて、長期間熟成した「十年熟仙」。クセがなくマイルドな味わいに仕上がっています。恐らく、販売用のしょっつるでは最長の熟成期間の一品。魚醤としては超希少な10年物を、是非お試し下さい」と諸井さん。
◉諸井醸造所
・
しょっつる諸井醸造所その1
May 23, 2011桧山納豆の次に向かったのは男鹿の諸井醸造所。三代目・諸井秀樹さんと久しぶりの再会です。
この↑桶は漬けたばかりで、ハタハタはまだフレッシュ状態!
整然と並ぶしょっつる桶ずらり。
蓋を開けると、ハタハタぎっしり!
ハタハタがこんなにもぎっしりつまって……と、いうのも、しょっつるの原料はハタハタ+塩。以上!
3年間じっくり熟成させると骨を残して液状になってくるのです。
ボディはシルバー色にキラキラ輝いて、ツブツブはブリコです。
諸井醸造所では、目の前の浜でとれた鮮度抜群のハタハタを使用。
そして
年度違いの桶をあけると!
ブラックベルベット!?
つづく
桧山納豆その2
May 21, 2011すばらしい!藁を編むテクニックを見せていただきました。
前日からの続き。秋田音頭♪で歌われている桧山納豆。元祖桧山納豆の西村庄右衛門さん、十四代と十五代目。
納豆を包む藁。どのように編むのか、見た事がないので、ぜひにとお願いして見せてもらいました。
稲わらは、「あきたこまち」を自然乾燥させたもの。
多いときで1日、ひとり200個以上編むという。大ベテランさんです。
ふたりで作業されています。こちらはベテランのお姉さん
そしてお姉さんより年下の妹さん。藁編みシスターズ!(って、血はつながってません)
壁面のカレンダーを見ると、数字あり。目標仕上がり個数ですね。2人で470個という日も(驚)
見ていると、形を作るのは結構たいへん。
あとでほどけたり、変形すれば納豆がうまく発酵できません。
もくもくと作業。手の動き、なめらかかつスピーディ。
船の形に編まれた藁。これがおいしい納豆のベッドなのです!
典型的な秋田美人のおふたりでした。
藁編みシスターズ♡に会ってから、桧山わらづと納豆が今までより余計においしく感じられました!
ありがとうございました。
◉元祖桧山納豆株式会社
社長さん。納豆、安すぎますっ。
このまま飾っておきたい!
桧山納豆
May 20, 2011♪秋田名物 八森ハタハタ 男鹿で男鹿ブリコ 能代春慶 桧山納豆♪
と秋田音頭で唄われる「桧山納豆」
こちら!秋田音頭
いってきました。元祖桧山納豆です。
早朝8時にうかがうと、大豆を圧力鍋で蒸している真っ最中。湯気もうもう
大豆は、地元能代市で栽培された「あきた白神大豆」。白神山地の豊かな土地、きれいな水で育まれた地元産100%。
甘い大豆のいい香りがあたり一面に
一粒いただきました。なにもつけなくても味が濃く、おいしい!
昔ながらの藁包でしっかり熟成させることで、噛み応えと粘りが出てくるのが特徴という桧山納豆。手編みした藁包を一度蒸し上げます。
大豆が蒸し上がると、いそぎ藁包に入れていきます。詰める作業を担当する女性たちもみなご近所さん。一番近い人は歩いて30秒!?
それは猛スピードで作業が進みます。
写真ではマジメそうに写っていますが、笑いが耐えない作業場でたいそうにぎやか楽しそう。
この稲わらは「あきたこまち」。杭かけして自然乾燥させたもの。もちろんこの近くで栽培されたものです。
14代目(と言われる)西村庄右衛門さん。
(右)息子の西村さん。15代目。
↓さきほどの藁包が蒸し上がりました。
アツアツです。
結構大きな機械なのです。
大豆を包んだ藁包を発酵の機械に入れてしばし待ちます。
「醤油よりも塩で食べてみてください」と十四代&十五代目。3ショットパチり。
混ぜるときはクルクルと横に回すのではなく、「縦まぜ」を教わりました。納豆を器に入れ、箸を上下に、空気を含ませるように混ぜるのです。塩味で食べると、大豆そのものの味、発酵した大豆の美味さがよくわかります。そしてお酒のツマミとしても楽しい!
この納豆は地元”能代の塊”ともいうべき一品。大豆、そして大豆を包む藁も能代産。そして水も、包む人もみ〜んなご近所さんという能代育ち。
土台の藁を船の形に編む、その様子も見せてもらいましたが、これまたビックリ。
藁を編んで半世紀以上の大ベテランさん!
つづく
_________________
◉元祖桧山納豆株式会社
いぶりがっこの里その2
May 18, 2011前回からの続き。
というわけで、雪の秋田へビューン。道は氷の上に雪が重なってツルツルの路面。何度もスッテンコロリンしそうに。
道の駅・ウッディさんない内にある御食事処 農香庵では漬物食べ放題!
そして、ありとあらゆる達人たちのいぶりがっこを販売。人生史上、これほど一度に見た事はないっというくらい見ました。あるとこにはあるもんだ。
そして!いぶりがっこ名人の高橋朝子さんを訪問。
朝子さんの秘蔵樽!いいにおい〜。
うぉ〜。迫力!
明るく楽しいラテン系の朝子さんです。本人は自覚していないと思いますが…。
自ら育てた大根を丁寧に燻し、添加物は一切なし。色づけに紅花を使うという贅沢さ。
真空パックマシン。
パック前のいぶりちゃんを俯瞰で撮影。整然と揃ってきれいです。
「スモーク加減にこだわる」という朝子さんのスモーク小屋。ブルーがキュート。燻す期間中は3時間おきに見にくるのだそうです。夜中もモチロン。そして時々、空気を抜いて燻しすぎないように加減するという。
家から小屋までずぼずぼと雪が深〜いのですが、「慣れてるから平気だ」と。夜中は真っ暗。知らない人が歩いたら遭難しまっせ。
樽から取り出したばかりのいぶりがっこ!わーい! 雪の照り返しが超眩しい。眉間にシワ3本のやまよ(オバQか)
ご自宅でごちそうになりました。この白い大根は「生漬け」とよばれるものです。塩漬け、それを柑橘の皮を入れて甘酸っぱくしたものなど。パリポリ爽やか。いい塩梅の三角食べ。
朝子さんと旦那さんです。食卓の右端にあるお菓子の空き容器、与論島の名があったのでお土産なのかなとふと尋ねると「毎年、雪を小学校に送ってんです」。「ほら、雪を見た事ないっていうから。今年は12箱送ったな〜」ど、どうやって?「発泡スチロールの箱に入れて、内容の覧に”雪”って書いてクールでね」なんと!
その御礼に小学生のお礼状と黒糖衣のナッツが届いたという。その空き容器でした。
「ふわっとした雪を選んでつめてね。雪合戦のときに丸めやすいように」きれいな雪がいいから、朝一番に山に行って取るという。家の周りにこんなに雪があるというのに。じーん。
リンゴ栽培農家でもある高橋さん。その小学校にリンゴも送っているそうです。「ほら、リンゴ食べた事ないっていうから」じーん。じーん。心やさしき高橋夫妻。
朝子さんはいぶりがっこ名人。いぶりんピックで何度も受賞しています。その賞状は、紙ではなく、トロフィーでもなく
樽!!!
そこで、せっかくなので受賞樽を見せてもらうことにしました。
「え?樽?ええっと〜」という感じで奥へ入っていった朝子さん。しばらくすると名誉の樽を抱えて戻ってきました。「樽な、場所が必要でな、飾るとこが難しくてな(笑)」
いや、ほんと。このボリュームでは受賞がつづくと置き場も大変!
朝子さんのいぶりがっこは燻しすぎず、甘さも抑えた自然の味わい。
樽の前で、こっそり秘密を教わりました。とある野菜を加えてみたという。「いい甘みと色もつくんじゃないかと思って(笑)」。なるほど。
名人といえど、技術磨きに余念がないのでありました。だから樽が重なってくるのでしょう。朝子さん、ごちそうさま&ありがとうございました。勉強になりました〜!
かわいいからもう1枚
いぶりがっこの里その1
May 17, 2011またまた2月の話へタイムマシーン!
今年は秋田とご縁がいっぱい。その1つがNHK『あきた・よる金』でした。「おもしろ大研究!秋田の日本酒」という番組を特集するにあたって、『純米酒BOOK』を読んだ担当ディレクターの上原さんから取材依頼があったのです。
秋田の日本酒のこと。それにあう食材を探す旅へとGO。
東京は青空。もちろん雪はナシの朝でしたが、秋田へ到着する頃になるとだんだん深い雪景色。まだまだ雪国秋田でありました。
今回は秋田の発酵食品を3つ訪ねる事に。まずは「いぶりがっこ」を求めて山内へ。
ちょうど最盛期で、いぶりがっこの糠を落とす水洗い中の人と遭遇。どうも〜。「どうぞ食べてみてください」と1本渡されました。お腹がすいていたので、嬉しかったです。ですが丸ごとをいただくのは初めてでした!歯が丈夫でよかった。
いぶり小屋。あちこちに雪捨て場が。
郵便局さん、雪道をバイクで配るの図。雪道運転ものともせず。(右)1本プレゼントしてくれたイブリのオジさま。
雪だらけです。
こちらもいぶし小屋。雪が重そうです。
ここもいぶし小屋。見回すとあちこちにいぶし小屋が。さすが本場。
↑漬かったばかり、糠を落とす前のいぶりがっこ。
取材前にお昼ご飯。道の駅・ウッディさんない
御食事処 農香庵では、漬物バイキング実施中。
製作者のフルネーム入。ここで気に入れば売店で買えると。嬉しいですね。手作り漬物食べ放題! さすがガッコ天国。
漬物の器。それぞれの好みが反映されます。山内のラーメン!
でっかいお麩入り!
私のじゃありませんが、お麩が面白かったので撮らせてもらいました。
風邪気味さんは鍋焼きうどん。
ここの名物は蕎麦!なのに誰も頼んでいないのはなぜ。お腹にたまらないイメージだから?
蕎麦と芋の子汁(山内は名産地)をどちらにするか、ものすごく悩んで(10秒ほど)
芋の子汁にしました!
大きなお椀にいっぱい芋の子ゴロゴロ
温まりました〜。やっぱ味噌汁だべ。山内の芋の子だべ。
食事後、店内の産直グループコーナーへ
ありとあらゆる漬物が
山菜が
粉が
いっぱい。メンバーの顔写真も。
お〜っ。サッカリン入。
漬物はいぶりがっこが一番種類がたくさんありました。
アップで!
フルネーム入。家々ごとに味があるのでしょう。
冷蔵ケースは2つあり、一方は従来の、そして一方は添加物ナシのいぶりがっこ。棲み分けされていました。HPによると「添加物、無添加」と分けられているようです。
ものすごい数のいぶりがっこでありました。
金樽も!
2011第5回目のいぶりんピックの様子
過去のいぶりんピックで金賞受賞歴数々の高橋朝子さんを訪ねました!
つづく
道の駅・朝日みどりの里
May 12, 20113月13日。秋田からの帰り道に立ち寄った道の駅「朝日」のこと(道の駅とPA、SA大好き。いちいち立ち寄るため、なかなか目的地にたどり着かない〜のが難)。ここは素晴らしかったです! 心癒されました。なにしろ、魅力的なオリジナル商品が山ほどあり。施設は道の駅だけでない複合施設で、物産会館に温泉も。心奪われたのは、写真の寄せ植えです。
寄せ植えは「セロリ、にんにく、わさび」。自分では考えもつかない組み合わせ。同じ土でこの3種は大丈夫なのかとビックリ。 緑の葉はそれはつやつや元気。しかも鉢はウッディな味あるプランター。形がどれもまちまちなところをみると、手作りプランターの模様。しかも! 値段が!
580円!! とベリー格安
その他にも、ユキヤナギや、春一番の行者にんにく
タラノメに、平飼い有精卵の卵は藁のパッケージ
地クルミも殻ごと、剥き実といろいろ。
用途が手書きされたじゃがいもや、干しもち草=よもぎですかね。しかし、どれも安い!
塩蔵たい菜、文字が二重線で消されて「どんぐり」と。どんぐりぃ? 右は「あさずき」? あ、「あさつき」ですかね。地方名が楽しいじゃありませんか。
ひゃ〜っ、真っ黒クロスケ!こんな真っ黒食べるんかいな…と思ったら「鑑賞用」の炭ですと。とうもろこしと松ぼっくり。なんでも焼いてみちゃったねと。
ドカーンとインパクトがあったお米。生産者さんの写真入です。写真入はどこでもありますが、この女性部隊の米袋には、それは心わしづかみ。特に左の鈴木アキさんの玄米こしひかり。家にお米のストックがなかったら即買いしたのですが、後ろ髪ひかれまくり…今でも。迷ったら買わなくちゃなあ。アキさんのお米求めに、また行きたい!朝日みどりの里。
米どころだからお酒も、酒粕もあり。「蔵人栽培 越淡麗仕込みの大吟醸新酒の粕」とそうでないのと、同じ蔵でも2種類。そして菊水酒造さんの缶シリーズもカラフル各種勢揃い。
ご当地ものたくさん、楽しい朝日みどりの里!
元気な農産物からは「こんなの出来たよ! 味わってみてよ!」とメッセージがいっぱい届きます。豊かな自然を背景に、伝統に裏付けされた知恵がつまった、活力みなぎる農産物バンザイ!
島田与一郎さんの寄せ植えをつれて帰りました。
1ヶ月たって、ボウボウに成長の図。さっさとカットしてたべなはれ状態。
しかし、3種類の寄せ植えで土がついて鉢がついて580円とはまったく。趣味のひとつなのかもしれません。島田さん楽しんでます!
滑川のホタルイカ6丸ごと&地酒
May 6, 2011滑川のホタルイカおさらいです。
富山湾に春をつげるホタルイカ。なんと一生はわずか1年間!
行為終了後、役割を果たしたオスは海底。メスは海上へ。上の写真、左側がオスで、右の大きい方がメスです。子孫を残して一生を終えるホタルイカ、なんと潔い人生でしょう。『神秘の光 ホタルイカ』
というわけで、前々回も紹介しましたが『ホタルイカのメスの各部位』調理By 倉本禮子さん。
お刺身は内臓、骨、目玉、卵をはずして、ボディと足にするのがナメリカワ流。「竜宮」スタイルと呼ばれています。これは澄んだ味わいが特徴。現地でしか、味わえないおいしさです。お刺身は本当に鮮度が命!
そして取り外された各パーツをそれぞれにおいしく!料理するのがホタルイカ名人・倉本流。
こちらはホタルイカの骨! これでおよそ200パイ分だそうです。こんなふうに食べたのは初めて!
↑こちらが元の骨。
骨を集めてかるく油で加熱すると、このようにパリッと美しいクリスタルな仕上がり。できあがりに塩をパラリで味わいかろやか、食感もグー! こざっぱりとして美味。
こちらは集めた卵と内臓をそのまま加熱したもの。ほどよい塩分があり、ふわりとして、うまみもたっぷり。何もせずとも超おいしいです。日本酒を欲する味(笑)。
こういう部位は骨ともども、つい捨ててしまいがちですが、なんのどっこい。単品がおいしい!
もちろん
丸ごとをゆでたてホタルイカも美味。
倉本さんいわく「ホタルイカはゆですぎないこと」が肝心。「色が真っ黒になると味も変わってきます。春を告げる食べ物ですから、桜色で。ゆですぎるとワタも出てきますしね」。東京のスーパーで”黒い”ホタルイカ、よく売ってますが、黒ではイカンのです。
ホタルイカの大定番料理、酢味噌あえはワカメ、ネギを入れますが、「昔は田んぼの土手にはえていたアサツキを入れたものです」と倉本さん。「セリ、三ッ葉もいいですよ」。なるほど、香りがあいそうです。
「昔は酢味噌をごちゃまぜにして出していましたが、今は酢味噌を別にしてます」食べる時に好みで酢味噌をつけられるよう、別添えにしているとか。美しい!
こんなホタルイカには、地元のお酒が一番!
滑川市唯一の酒蔵、千代鶴さん。「恵田」いただきました。
富山湾の海底を思わせるロイヤルブルーカラーのお酒も。
大観峰のお土産として名高い「まぼろしの酒 大観峰」は陶器入りの酒。
地元のお米で仕込んだ「恵田(エデン)」
蔵にもどって9年目。今季のお酒で初の入賞を果たしました。おめでとう黒田一義さん! 訪問した前日が受賞式。記念の賞状の前でゴッド大谷と三人で記念撮影を。おばちゃんに囲まれて(困ったであろう)黒田さんであった。
平成22酒造年度金沢国税局酒類鑑評会 優等賞受賞
●滑川観光情報
なめりかわ宿場回廊巡り
海沿いの道には、古い建物が残っています。
こちらは元酒蔵。改装して、イベント等に利用されているそうです。
奥の奥まで蔵がつづいています。
現役のポストも味があります!
滑川のホタルイカ5絶品昆布巻
May 4, 2011前日からの続き。倉本さんの料理で何が大感動したかというと、ホタルイカはもちのロンなのですが、昆布〆です! 菜の花をさっと塩ゆでし、昆布で〆たものをいただきました。あまりにおいしそうで、それだけおねだりしていただいたのです。
それはそれは、それは!!ものすごいおいしさでした。もう、これだけで、これさえあれば!状態に。頭に浮かんだのは「あの」きれいなお酒と合わせたいと思い浮かぶ始末。
富山は全国で一番、昆布の消費量が多いそうですが、一般家庭でこれだけ昆布を大量に上手に使いこなす県はないように思います。富山では「昆布〆用の昆布」が売られています。
その絶品菜の花!(しつこいですが、それは感動的なおいしさで一緒に口に入れたゴッド大谷と思わず顔を見合わせ「うぉ〜っ」と叫んでしまったほど。倉本さんちのご主人、お子様は毎日、こんなおいしい料理を食べているわけで。そりゃ一族が30人にもなるわけですなあ…などと思ったり)
それだけでおいしい菜の花の昆布〆に、青じその葉、さっと茹でたホタルイカをロールUP!
見事であります。昆布もほどよい柔らかさ。昆布+菜の花+ホタルイカの三位一体。ナメリカワ、おそるべし。
« Previous Entries Next Entries »