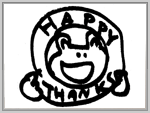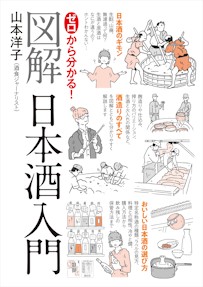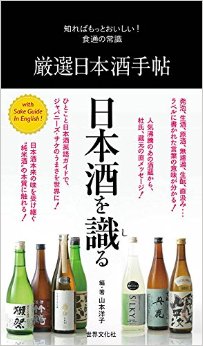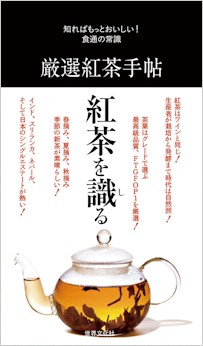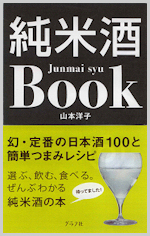日本酒
« Previous Entries Next Entries »天の戸・森谷康市杜氏の田圃
November 5, 2014収穫前の天の戸・美山錦田圃 photo 森谷康市杜氏
これから発売になる「日本酒手帖」ですが、編集するにあたって酒米の田圃がよく伝わる写真を探しました。一番田圃のいいところを撮影できるのは、育てている本人でしかありえません。しかも、写真が上手となると非常に限られます。
この人は!と見込んだのは、「天の戸」醸造元・浅舞酒造の森谷康市杜氏。お願いしたところ、それは素晴らしい写真をお持ちでした。杜氏の田圃の酒米は「美山錦」です。
以前、杜氏がぶどう畑で「おいしいものができる畑は美しい」と。酒米の田圃もそうなのだと染み入る写真ばかり。緑色の文字は森谷杜氏にいただいたコメントです。おいしい日本酒の背景には、こんな感動的な田圃があるのです。
・
天の戸・森谷杜氏の田圃
Gallery
この風景をビンにつめたいと思います。
春は一面が水鏡。奥羽山脈に端を発する皆瀬・成瀬の川は横手盆地に沃野を生み、広大な田んぼをうるおします。
そして、その川の一部が伏流水となって蔵の近くに仕込み水となる湧水群をつくります。
・
慣行栽培の半分まで農薬を減らし化学肥料も極力減らした「特別栽培米」。
少しずつ虫が増えました。少しずつタニシが増えました。
明け方、細かい霧をまとったクモの巣が逆光に浮かび上がります。
そろそろタニシを食べにカラスやサギがやってくる頃。
・
稲は雨が降ろうと風が吹こうと受粉します。
それは「もみがら」というカプセルのなかでの交配となるからです。
われわれが稲の花と思っているのは受粉の役目を終えた雄しべが「受粉完了しました」の合図に出てきたところを見ているんですね。
・
秋に靄のかかる土地は良い米ができるとききました。
雨がふらなくてもこの露が稲の穂を保湿し、稲の枯れ上がりを防いで稔実を高めます。
コロコロした厚みのある酒米ができます。
・
雨が降ると葉を広げます。風が吹くと根をしっかり張ろうとします。
お天道さまが照らない日もしっかり仕事をしています。
・
酒米は一般に大柄な稲が多いです。
その体についた茎だから太いはず。
でも米が充実してくるとその重みで太い茎をしならせます。
・
酒米・美山錦
・
撮影すべて浅舞酒造・杜氏 森谷康市さん
天の戸・浅舞酒造facebook
うどん県それだけじゃない!うどんに合う酒?
November 1, 2014ひとつ前のブログ続き
「うどん県それだけじゃない!香川県」オリーブ&オリーブハマチの説明を聞いている最中、テーブルにドンっと置かれた酒が「うどんに合う酒」!? ラベルのデザインもなんだか大胆
オリーブハマチに合うんじゃなくて、うどんに合うの?
香川県の米「オオセト」使用
お酒の企画は「うどんに合う酒を考える会」
賛同した西野金陵、綾菊酒造、森国酒造の3蔵が ”県産米を使用し、うどんに合う純米酒を考えた”という。
壇上では鏡開き!うどん脳くんも首をかしげながらin。うどん脳くんは頭が大きく、手が短いことを知る。
香川の日本酒といえば!金陵、国重、川鶴、そして悦凱陣
楠神と書いて、くすかみと読む。
西野金陵さんの特別純米酒「楠神」は「酒造りの守木である樹齢900年の大楠から採取した天然酵母」で醸した酒。オオセト100%使用。楠から採取した酵母は初めて。「うま味のある酸味が特徴」と。いろんな酵母があるもんです。
そして!こちらが「うどんに合う酒」
蔵元は、西野金陵(琴平町)、綾菊酒造(綾川町)、森国酒造(小豆島町で唯一の酒蔵)の3社
「うどんに合う酒」があれば、「酒に合ううどん」もあるという
左はノーマルうどん。右が「酒に合ううどん」で、2012年に開発。県産小麦と県産米「おいでまい」に県産茶を練り込んだ麺。のどごしの良い爽やかな風味がウリという。
http://www.kensanpin.org/umaimon/recipe/sakeudon/
皆さんにお酒をすすめる高松シティホテルの社長・富永博道さん。うどんに合う酒のPR隊長です。
3蔵ともそれぞれの味
↑綾菊酒造さんは山廃仕込みで「さぬきよいまい」使用。
うどんにどう合うのか?質問すると、それぞれのお蔵さんで考えが違うという。お蔵さんに聞くと「じつは、難問でした」と。
ワタクシが思いますに、まずは、酒を口に含んで、つゆをつけないうどんを食べる。すると、口中に、小麦の味がグンと開く。次に、つゆをつけたうどんを食べて、酒を飲む。すると、小麦とつゆのうまみが、酒のうまみと重なり合って、豊かに広がる。そんなうどん酒なら飲んでみたいですわ。でもうどんはうどん。蕎麦とはちょいと違います。どこを捉えるかが鍵?
「酒に合ううどん」は県産小麦に、米、茶入りで微妙なカラー
こちらはプレーンのうどん
お酒と、試してみました…。
うどんはお茶の風味が少しして、これはこれで悪くないと思いますが、お茶の方が合うのでは!?と素朴な感想。
思いますに、瀬戸内海に面した香川県なので、魚介類を季節限定で練り込んでも面白いのでは?と。
味の濃い小エビを干しエビにして細かく入れるとか、海苔養殖も盛んなので、海藻を入れたらどうなのでしょうね。季節によって、春はサワラ、夏はマナガツオ、秋はチヌ、冬はハマチ。その他にタコも有名!珍味・亀の手もあり。海の幸と手を組むと、もっと日本酒に合いそうだと思います。現地でしか食べられない、とっておきのうどん開発!期待しています。
●香川の魚市場、瀬戸内四季・旬の魚
その他に「讃岐三畜」讃岐牛、讃岐夢豚、讃岐コーチン
香川県が日本一の生産量という金時にんじん。色鮮やかでお正月以外にも使ってみたい人参です。
クルマエビの養殖は香川県高松市で始まったという。そして、サヨリと穴子など、寿司ネタも多い香川県。
うどんの薬味は生姜とネギ
ぜひ、皆さん!
全国から名物うどんが集結する
「全国年明けうどん大会2014inさぬきをよろしくお願いします」と、うどん脳くん。
●「さぬきうまいもん祭りin東京」 shot
料理は他にも「ゲタのから揚げ」「マダイのから揚げ甘酢餡」etc. 希少糖はヨーグルトのシャーベット仕立てで登場。
「小豆島のオリーブ新漬」なども!瀬戸内海の気候を活かした食材がいっぱい。
確かに、「うどん県、それだけじゃない!香川県」でありました
11月27日は純米酒×和食@メトロポリタン秋田
October 29, 2014東北の中でも、宮城、山形、秋田の日本酒は県全体のクオリティが高くておすすめ県! その中でも、秋田はクオリティに加え+個性派揃い目が離せません。
酒米も「秋田酒こまち」や「美郷錦」、「吟の精」など魅力的な品種がいっぱい。
各蔵の取り組みも、オリジナル酵母に、黒&白麹まであって、毎回、訪問するたびに感動しています。
ホテルメトロポリタン秋田で、その秋田の純米酒をたっぷり楽しむイベントが!!!
秋田Love♡な私がお酒をセレクト。山上料理長が考えた時間をかけたとっておき酒肴が勢揃いします。
「秋田産純米酒と和食を愉しむ会」 セミナーと秋田純米酒×和食を楽しむ二部構成
スパークリング、純米大吟醸、純米吟醸、純米を温度違いで各種。
それらに合わせて、精進出汁や、「河豚のたたき」、純米酒を使った料理長特製の酒塩麹に、ピリカラ青南蛮麹!
「ずわい蟹と干柿の掻き揚げ」や「松茸と豆腐の万年漬け」、「秋田仕込み!?の新唐墨」も(ただ今、料理長が絶賛製作中!)
秋田のフルーツがおつまみで登場です! 料理長からレシピも教えてもらえますよ。
今から楽しみ×楽しみ〜なのでございます! :-o
http://www.metro-akita.jp/event/event_sake2014.html
静岡・伊東の魚と誉富士純米ツアー!
October 27, 2014以前、このブログでお知らせした
「静岡・伊東の魚と誉富士純米ツアー」
好評につきバス増発となりました。
とはいえ、HPではあまり詳しい情報はのっていません。以下のことくらい。
・「波魚波」の新鮮朝獲刺身定食の昼食・木造3階建和風旅館「東海館」見学・魚市場特設「いとうウオイチBAR★」・「誉富士」6銘柄以上の飲み比べ、きき酒大会 イケメン蔵元さんも・飲み比べ時に、地元おつまみ(ちんちん揚げほか)試食・いとう漁港のおつまみセットのお土産付き などなど
勿論、これで 5,500円はお・と・く!
先日の打ち合わせ風景。伊東漁協の山本香織さん、静岡県経済産業部農林業局茶業農産課の平形裕子さん、村松班長、専門監 遠藤和久さん
ランチの定食、そして酒の肴にも、いとう漁協の自慢の魚がズラリ! そしてお米も醤油も山葵もトビキリの静岡産を予定
ウエルカムドリンクを、どの蔵の何にするか、熱く検討。当てたら相当凄い!
打ち合わせは、静岡漁連が入っているお堀の隣、通称黒ビル1階のパンカフェ パン・サンジュで。
このパンカフェに、いとう漁協のさば男くんを使ったバーガーがあるという。
これです!その名も
「さば男くんバーガー」注文してみました〜
お肉が苦手なワタクシ向き!
じつは、さばを使ったバーガーはもう一種あり
「さばじゃが君バーガー」
「さばじゃが君」は、生協、農協、漁協がコラボして作ったメンチだとか! 次の機会があったらコレ試してみよっと心に誓う
11月8日、ツアー当日は、自慢のサバを使ったアレコレ、イケメン漁師に蔵元さん登場!
「山と田んぼと海が繋がって、また新たな結合が生まれる予感!!ワクワク」と平形裕子さん。ワタクシもです!
どうぞお楽しみに。それでは、いとうで!
ダイヤモンドでニッポンの酒特集
October 27, 2014清水量介さんが愛と力を注ぎ込んで編集した最新号の。喜久酔の青島孝さん、秋田のNEXT5、獺祭の桜井さんと中田さんの対談、而今の大西さんも登場。世界へ羽ばたけ日本酒!
日本酒セレクトを依頼され、北から選んでいったら、西の酒蔵が入らなく…m(__)m。
醸造は農業と深く連携していること、「一日一合純米酒」のことも紹介してくれて、嬉しい‼︎*\(^o^)/*
ダイヤモンド編集部の清水量介さんが愛と力を注ぎ込んで編集した最新号 週刊ダイヤモンド 2014年11/1号 「世界が認めたニッポンの酒」。
栽培醸造家である喜久酔の青島孝さん登場!
秋田のNEXT5の皆さん。それにしても、もうちょっと皆さんお顔なんとかならなかったのかしら…。
その他、獺祭の桜井さんと中田さんの対談、而今の大西さんも登場。世界へ羽ばたけ日本酒!
日本酒セレクトを依頼され、北から選んでいったら、西の酒蔵が入らなくなりました…m(__)m
編集者の清水さんが、”醸造は農業と深く連携している”ことを書いてくれました。
「一日一合 純米酒」のことも!
飲んでおいしいのは勿論のこと、おいしいを超える酒が純米酒なのだということを、これからも伝えていきたいです。
撮影 iPhone5
20141025朝カル「普通じゃない普通酒」
October 25, 2014ひとつ前のブログで紹介 http://www.yohkoyama.com/archives/68812
10月25日の朝日カルチャー教室「楽しむ純米酒」講座は
「普通じゃない普通酒」がテーマ!
獺祭さんの「山田錦23% 破砕米」を使った「試(tameshi)」、飛良泉さんの「秋田酒こまちの等外米35」=「飛良泉35」、初亀さんの「兵庫県産山田錦で 1.9mmで等外」になった「初亀 縁 プレミアム pure」など様々。
その他にも、掛米に等外米を使ったものなど、米・米麹だけの酒ですが「純米酒」を名乗れない理由様々。
おつまみは味わい違いで3皿を出しました。
一皿目は、繊細なお酒の味の邪魔をしないもの。かまぼこ(鈴廣)+わさび漬け、ひたし豆、きゅうり+香り味噌、用宗漁港のしらす、お刺身イカのさっと茹でホワイトセロリあえ、中川さんちのカボス添え
本来、「普通」はいい意味のはず。
混ぜ物だらけの一般普通酒は、消費者に違いがわかるようにしてほしいものです。添加している、醸造アルコール、糖類、酸味類、アミノ酸類添加をもっと文字を大きく、明確にしてほしい。
醸造アルコールというアルコールは「醸造酒」と思い込んでいる人がほとんど。これがどっこい蒸留酒。ホワイトリカーみたいなものだというと皆さん、ビックリされます。
日本酒を普段飲まない人は、そんな差があることすら知りません。
そんな普通酒を飲んで「日本酒がマズイ」なんて言ってほしくありません
2皿目は、野菜やキノコのおひたしやあえものです。
左)エリンギと水菜、上)小松菜と油揚げとかつおぶし、右)いんげん豆と鱧竹輪(酒粕あえ)
お酒はここから、日置桜さんの「夜桜」、辨天娘さんの「青ラベル」、鷹勇さんの「鷹匠」。この3種を常温とお燗酒55℃〜60℃で提供しました。お燗すると答えられない旨さです!
おつまみ3皿目は、ハタハタ塩麹漬け焼き。いぶりがっこ、チーズ。そして、辨天娘さんの愛しの奈良漬けです! その昔、木村 敬さんに教えてもらってからハマり、affで取材させてもらいました。塩漬け3回、酒粕に7回以上漬け直す珠玉の逸品!大根とキュウリの2種あり。
酒蔵と酒販店はひとつ前のブログで紹介。
普通じゃない普通酒
October 24, 2014明日25日(土曜)の朝日カルチャーセンター「楽しむ純米酒http://bit.ly/YoTCp9」のテーマは「普通じゃない普通酒」です。
原材料は「米と米麹」だけ……なのに「純米酒」と名のれない酒があります。
それが、”ワケありだけどうまくて安い” 米だけの酒。
一般に売られている「普通酒」とは酒質が月とスッポン!!
なのですが、分類上の名前は一緒…。
普通酒の定義とは、酒税法でいう特定名称酒以外の清酒をいいます。
米・米麹・醸造アルコール「以外」の原料添加が認められたお酒です。
なのに、それらを入れないことがモットーの全量純米蔵が「普通酒」を造るのはどうして?
その理由とは? 味とは?
そんな ”ワケありだけど、おいしい普通酒” を飲みながら、蔵の背景にある地域力、蔵の個性を学びます。
酒蔵地域のおつまみといっしょに:-o
●獺祭「試」 虎ノ門マスモトさん
●喜久水「どうらく酒」 天洋酒店さん
●飛良泉「35」
●初亀「縁 プレミアム pure」 酒舗よこぜきさん
●日置桜「夜桜」谷本酒店さん
●辨天娘「青ラベル」谷本酒店さん
●鷹勇「鷹匠」谷本酒店さん
・
などなど〜。どの蔵も、素敵なワケありの酒ばかり!
お楽しみに!!自分が一番楽しみにしているという(笑)
そんな米・米麹だけの「普通」な銘酒が勢揃いです!
国民文化祭あきた2014
October 13, 2014撮影/木川伸一さん
11月8日発売の「厳選日本酒手帖」の校了真っ最中ですが、秋田で開催された国民文化祭あきた2014・食文化シンポジウムのパネルディスカッションに参加してきました。
民俗学者の神崎宣武先生がコーディネーター。AIU勝又教授、佐竹知事、沢の鶴(株)西村社長という日本酒好きメンバーが集合です。
私は開催地が秋田であることに、深い意味を持つと。酒は米から、実りの「秋」の「田」んぼからスタートです。今まさに、酒米の刈り取り真っ最中!
日本酒造りには、秋田の天然杉が重要な役割をすることをお伝えしました。刈穂&出羽鶴の伊藤洋平さんに麹蓋をお借りして、説明を。そして秋田杉をくり抜いて作った酒器も紹介!
撮影/伊藤洋平さん
麹蓋は、天然秋田杉の柾目を手斧で作るのです。この箱を作ることで様々な技術の継承が行われます。杉の酒の舞台での活躍が伝えられて良かったです。
塩麹は酒で仕込むと美味しい話、桧山納豆の社長さんに伺った「塩で縦混ぜするとお酒にあう」ことなども。この後、何人もの方から「知らない話がいっぱいでした!」と声かけられました
米の酒、日本酒は、農業、林業、窯業、漁業までつないでいます!
そのことを次の本でも少し、ご紹介しています。
それにしても、佐竹知事はオモシロすぎます!大爆笑の渦でした。
撮影/東海林剛一さん
癒やしの深夜の子持鮎甘露煮
October 3, 2014一日があっという間に過ぎていきます。時間の使い方がドヘタです。
次の5日が脱稿なので、頑張らねばなりません…が日付も変わり、1時半も過ぎましたら「店仕舞いしてもよござんしょ」な気分。シャッター(心の)ガラガラ。一杯飲みたいと思います
先日の秋田TRIPで一番の大事な出来事がUPできていないのです。それは宝物のような事なので、きちんと紹介するのです〜。
さて
10月1日の「日本酒の日」に送ってくださった奥播磨の下村裕昭さんありがとうございます。蔵近くの揖斐川で採れた子持ち鮎の甘露煮だそうです!調理したのは魚屋兼仕出しやさんだとか。甘露煮されても結構な大きさ。もとはどれだけ大きかったのか。この卵が自然界に戻らず、どうもスミマセン な気持ちでありがたくいただきました。
なんでも、作り方は、一度焼いてから甘露煮にしているそうです。
じつは甘いものがちょいと苦手な私です。特に飴炊きのようにカチカチに甘い甘露煮は、超ニガテですが、こちらは品のいい甘さで、サクサクしています。一尾をおいしくいただきました! 和みました〜。ありがとうございます。調子にのって飲み過ぎないようにします(笑)。それではお休みなさい。明日もがんばりましょう!気合だ!(自分、激励中)
撮影 iPhone5
秋田TRIP・日の丸醸造の内蔵
September 25, 2014秋田TRIPの続き
くらをの鈴木百合子さんが「この後、まんさくさん蔵にも行かれますか? 蔵の町といっても、うちがそうだと思われると困るので(笑)」
増田町は蔵の町として売りだしています。
http://www.city.yokote.lg.jp/tokusetsu/masuda/04_open/index.html
とはいえ、家の中にある内蔵なので、外からはまったくわかりません。豪雪地帯ゆえに、家の中にあるのです。写真は↑その「まんさくの花醸造元・日の丸醸造」さんの内蔵です。
座敷奥の立派な扉
開けるとまた扉
その上の階。梁の太さ、柱の間隔に注目!
柿渋を入れていたという「かめ」
9月初旬、酒蔵のあちこちを造りにそなえ、修復中
麹室内、待機中の麹蓋
「かもすぞー」の作者も蔵に来訪。直筆サインもあります。こちら↓もやしもんによる自己紹介!?
酒米も展示。右端2種がダントツ背丈が長い!
厳冬期には、この窓がすべて雪が積もって覆われてしまいます。今は想像できませんが!
この屋根の上も雪がドカッと。雪下ろしで大変。ひやおろしならぬ「雪おろし」という商品が限定で販売されます。
蔵には日本のお宝がいっぱいつまっています。
◯2011年の訪問
http://www.yohkoyama.com/archives/29958
◯2009年の訪問
http://www.yohkoyama.com/archives/12442
●増田町HPより↓抜粋
日の丸醸造本社 (国登録有形文化財)
〔特徴・見所〕
元禄2年(1689)、沓澤甚兵衛が創業した「日の丸」は、大正2年(1913)年の日英大博覧会で1等金牌を受賞しました。大正14年(1924)に株式会社化し、戦時中一時廃業したものの、昭和23年(1948)年復活し、現在に至っています。 店舗は街道に西面して建つ平屋建ての建築です。妻面は化粧梁と化粧束、そして、その間の漆喰壁とが創り出す黒と白の対比が美しく、店舗に掛かる下屋庇と、主屋の大きく緩やかな屋根と相まって、伝統的な町家の様式を伝えています。内部は増田の商家らしく、南側に吹き抜けの「通り」を配して、店舗から醸造蔵まで屋内を往来できるようにし、同時に、家の中心部まで光が届くよう高窓を取り付ける工夫がなされています。北側には事務室、応接室等を配し、その奥に居住スペースを設けています。 この時期に建設された内蔵は、各蔵ごとに工法や意匠に工夫がなされ、当家の場合は5寸5分のヒバの通し柱を1尺間隔で配することで、堅牢な構造を創り出し、梁や小屋組を支えて他家の土蔵よりも階高の高い広い空間を作り出しています。また、小屋組も他家の物とは異なり、伝統的な重梁工法を用いながらも、使用されている小屋梁には元口2尺5寸の欅が使用され、その巨大な小屋組は見る者を圧倒します。 装飾に関しては、土蔵全体が黒漆喰で仕上げられ、土扉と冠木は磨き仕上げが施されています。土扉を飾る鞘飾りには、大戸や内部の欄間と同じ亀甲の組子細工が組み込まれ、漆塗りで仕上げられています。 1階の内部は、狭い間隔で立ち並ぶ柱や梁に漆が塗られ、柱間の白い塗込めの壁とが織り成す絶妙なバランスが、室内を凛と引締め、気品ある美しさを漂わせています。また、座敷の装飾にも当時の新しい素材であるガラスも取り入れられ、伝統的な工法と、最新の技術や素材を融合させて造られた、究極の土蔵と言って過言ではありません。
増田の内蔵豆知識
« Previous Entries Next Entries »