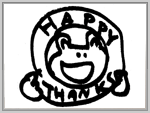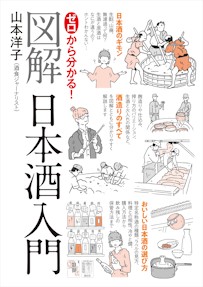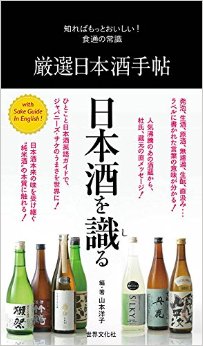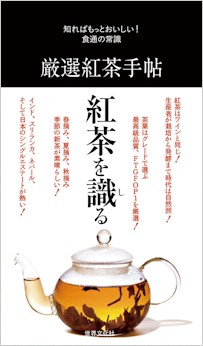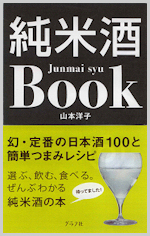日本酒
« Previous Entries Next Entries »次の朝カルは「八十八夜に楽しむ純米酒」
April 21, 2014新茶の季節ですね。写真は静岡県沼津市の山二園さんの「さえみどり」です。母は「やぶきた」父は「あさつゆ」を交配した品種。清々しい新葉のグリーンを見ると、”夏もち〜かづく〜八十八夜♪ ちゃんちゃん♪”が口をついて出ます
さて、今月の朝日カルチャーセンター「楽しむ純米酒講座」は4月26日土曜日
テーマは「八十八夜に楽しむ純米酒」
「夏も近づく八十八夜♪」でおなじみの八十八夜は、立春から数えて88日目。八は末広がりで縁起がよいことから、夏支度を始める吉日。
また、八十八は組み合わせると「米」であり、まさに米を思う日でもあるのです。
そこで、夏直前、八十八夜に相応しい、銘茶どころの日本「酒」8種類と日本「茶」、新茶を使ったおつまみなども合わせて楽しみます。お茶は自然仕立て、手摘みの極上新茶をご用意します
●朝日カルチャー「楽しむ純米酒講座」
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=239484&userflg=0
____________________________
●山二園さんを紹介したブログ
↓↓
●2013 山二園さんの新茶さえみどり
●2013 沼津・山二園さんお茶祭り
●2013 沼津発 おいしい感動をつくる仕事・山二園2
●ぶれないお茶~山二園 日本一の受賞茶を楽しむ会~
一番茶しか作らない、山二園の後藤ファミリーです!
山二園のマダム後藤に教わった煎茶飯(グリーン色!)の作り方も伝授します!
20140416「新世代栃木の酒2014」
April 19, 2014↑「とちぎ酒14」100%で醸した純米酒を試飲
「新世代栃木の酒2014」ご参加いただいた皆さん、蔵元の皆さん、酒造組合の齋藤さん、お世話になり ました!
講演タイトルは
「農・水・山をつなぐ下野杜氏 とちぎ酒米の魅力を探る」です。
目玉は、栃木県オリジナル酒米・特に今年は希少な(よくぞ集めてくださいました。感謝!)「とちぎ酒14」を97%精米で ”炊き”、栃木県産コシヒカリと比べて「酒米と飯米」を味わってみようというコメクラーベ企画。めったにないチャンス! 酒米の粒の大きさにもたまげてもらえたと思います。
食べたあとは、同じ米を飲む!であります。
「とちぎ酒14」100%で醸した純米酒を、3つの酒蔵さんで飲み比べ。同じ米でも精米違い、醸し方でこう変わる!が実感できたかと
速醸もとで「望」60%、「松の寿」65%
そしてきもと造りで「旭興」88%!
炊飯器4台フル稼働
この酒米を、最初に試験醸造した井上清吉商店の井上さんから、この米の誕生経緯などお聞きしました。
その時代、時代に合わせて酒米が生まれたことなど、日本酒の流行、変遷を感じた一幕でした。それぞれの米の特性をはかり、どう考え、育てあげるのか。米と水だけのお酒だからこそ、極めることが山ほどあります。
精米歩合、酵母の組み合わせ、速醸、山廃、きもと造りetc.
旭興さんは「とちぎ酒14」をまず77%でチャレンジしたあと、88%へ。そして、まだまだいけると99%にもチャレンジ!( その酒は気になる香りから「オーク樽貯蔵酒」にしたという)
ひとつの米の徹底解剖は勉強になります。
「大那」醸造元・菊の里酒造の阿久津さんはほとんどの酒米が近所の農家さんと契約栽培。「米と水でしか造らない日本酒だから、米にこだわる」がモットー。
それにしても「とちぎ酒14」大粒でふんわりとした甘み、冷めてもモチモチ感は食用米でも活かせばいいのでは〜!とも思うほどでした。おむすびでも美味しい、収量も多く、ゆえに米代も安い。なんとも健気な米「とちぎ酒14」であります。
最前列で聴いてくれた土’馬十駕の池田聖子さんが写真を撮ってくれました
栃木は世界遺産の日光や宇都宮の餃子が有名ですが、意外なくらいの森林+農業県なのです。
森林+農業用地で県全体の約75%も占めています。
鹿沼土は全国区でも有名なブランド土。
苺は44年間ずっと一位。二条大麦も一位。酪農は全国で二位。意外なほどの農業県。「酪農が多いので、有機堆肥の牛糞にも事欠かかない」と大那の阿久津さん。
県内ベスト5の山はすべて2,000m越え。そして一級河川多し。田んぼに酒蔵に、水が潤沢にあり、枯れたことがないというのも、当然なわけです。
そのダイナミックな自然背景を武器に、各蔵元が個性を出し(甘酸っぱいの、きもとonly、オーガニックetc.)表現しているのが栃木の魅力だと思います。
_____________________________
◎第二部・備忘録
●栃木酒造組合直営・酒々楽
●「とちぎ酒14」滝田稔さん
●新世代栃木の酒2014
本日は新世代栃木の酒2014
April 16, 2014お天気よくて嬉しいモーニング!今日は栃木県酒造組合主催「新世代栃木の酒2014」でございます。
16時45分より、講演させていただきます。タイトルは「農・水・山をつなぐ下野杜氏 とちぎ酒米の魅力を探る」です!
今回の目玉は、栃木県オリジナル酒米・特に今年は希少な(よくぞ集めてくださいました★)「とちぎ酒14」を97%精米で炊き、栃木県産コシヒカリと比べて味わってみようという企画。粒の大きさにたまげてください。
その後、3つの酒蔵さんによる「とちぎ酒14」純米酒飲み比べ! 同じ米でも醸し方でこう変わる〜が実感できます。あの蔵の88%!も登場です 予約不要ですが第一部と第二部(チケット完売)に参加する方で、先着100名様限定。
*なのですが、こんな大事な日だというのに、唇の下にカサブタを作ってしまいました。唇の下に海苔を貼ってるわけではありません。あらかじめお断りしておきます
お天気よくて嬉しいモーニング!今日は栃木県酒造組合主催「新世代栃木の酒2014」でございます。
16時45分より、講演させていただきます。タイトルは「農・水・山をつなぐ下野杜氏 とちぎ酒米の魅力を探る」です!
今回の目玉は、栃木県オリジナル酒米・特に今年は希少な(よくぞ集めてくださいました★)「とちぎ酒14」を97%精米で炊き、栃木県産コシヒカリと比べて味わってみようという企画。粒の大きさにたまげてください。
その後、3つの酒蔵さんによる「とちぎ酒14」純米酒飲み比べ! 同じ米でも醸し方でこう変わる〜が実感できます。あの蔵の88%!も登場です 予約不要ですが第一部と第二部(チケット完売)に参加する方で、先着100名様限定です
この蔵元に会える!
この蔵元にも! 水も美味です
どんな新酒が集まるでしょう! 楽しみです
*なのですが……こんな大事な日だというのに、唇の下にカサブタを作ってしまいました。唇の下に海苔を貼ってるわけではありません。あらかじめお断りしておきます
栃木酒造組合直営・酒々楽
April 14, 20144月9日に栃木に行った時のこと。栃木酒造組合直営の酒々楽さんへ打ち合わせの後、初訪問! 念願叶いました〜!
●blog「とちぎ酒14」滝田稔さん
全蔵のお酒がひとグラス100円で試飲できるという!
ショーケースが冷蔵庫に。お酒は酒蔵さんが選んで持ってくるそうです。
テーブルには資料のファイルがおかれ、蔵+酒情報がわかります。
他の飲食店の営業妨害にならぬよう、5時から7時まで2時間だけの営業(土日休み)
試飲手順は
まず、チケットを購入し、カウンターで番号を言う。本日のおすすめ3点セットなんてのもあり
ファイルには、各お酒の説明が
その数、120種類。よりどりみどり!
質実なインテリア
簡単なおつまみも。テーブルにはお水もセット
米違い、酵母違い、蔵違いでいろいろ、少量ずつ試せるのは嬉しい!
ラジオ体操のようなカードを持っていたオジサマに、そのカードを見せてもらいました。飲むたびにスタンプを押してくれるとか。制覇すると特典が!
・・・なんでも、決まった銘柄ばかり飲まないよう、いろいろ試してほしい酒造組合で考えたカードだそうです。全蔵飲んだら、達成感ありますね!
栃木のイケメン2蔵元、左)大那を醸す菊の里酒造の阿久津信さん、右)澤姫を醸す井上清吉商店の井上裕史さん。酒々楽では、時々蔵元dayもあるそうです。
酒々楽は酒造組合の1階にあります。
その蔵がどんな味なのか、ちょっとだけ試してみたい人には(私ですよ!)天国のようです。
迷っちゃうリンダ♪となりそうですが、営業時間が短いので、判断は早く。全国の酒造組合でつくってほしい!
栃木県酒造組合
酒々楽(ささら)アクセス
〒321-0352
栃木県宇都宮市本町12-31
TEL 028-622-5071
FAX 028-627-1780
営業時間
17:00~19:00
(土日・祝祭日を除く)
※座席数30席
●栃木県酒造組合
酒々楽(ささら)
〒321-0352 栃木県宇都宮市本町12-31
TEL 028-622-5071 FAX 028-627-1780
営業時間 17:00~19:00 (土日・祝祭日を除く)
座席数30席
獺祭・旭酒造の桜井博志さん「逆境経営」
April 12, 2014 獺祭・旭酒造の社長 桜井博志さんが本を出されました。タイトルは四文字!
「逆境経営」
発売直後に売切れ、増刷という
カネなし! 技術なし! 市場なし! つぶれかけた酒蔵の七転び八起き
ことわかりにくい日本酒の世界。それを、シンプルで力強い方法で切りぬけてきた桜井さん。銘柄は「獺祭」1銘柄のみ。すべて純米、しかも大吟醸。使用する酵母は9号で酒米は山田錦。ゆえに全商品、味の軸が揃い、精米歩合、搾り方違いで選ぶだけ。消費者にわかりやすいことこの上なし。
・・・
やたら種類と銘柄が多く「売れない」と嘆く蔵元さんがいたので、獺祭さんのシンプル商品群の話をすると「あそこは売れてるから、特別」といわれたことが。
なぜか「売れないから、考えた」が通じないのです。売れない理由を酒以外にしたい感じです。売れる商品をつくる前に「負」の商品をなくすことからだと思うのですが。
これは、なにもお酒に限りませんが…。
以前、桜井さんに聞いた言葉で印象的だったのが
「獺祭は技術がないので、最高の酒米・山田錦で、純米大吟醸しかつくらないのです。100m競争で、5m先に出てスタートダッシュするようなものです」
「さすがに同じことばかり続けると、気づくことが多いですよ。そのつど改良を加えます」
「獺祭の雄町を飲んでみたい、獺祭の山廃を飲んでみたいという方がいますが、二度と騙されません」
好きなことをいう人は山ほどいます。どの意見を取り入れるか。
桜井さんはメールマガジンを書いてます。それをまとめたのが「逆境経営」で、本には大失敗した地ビールの話をはじめ、失敗談がわんさか。
●桜井語録
「地元でまったく相手にされず売れないから、泣きながら東京市場にいったんです」
「東京の酒販店で名刺を出したら ”はあ?山口?どこ、獺越?聞いたことないねえ。はっは〜、山口の〜、山奥の〜、ちーさな酒蔵かあ” と、バカにされましてね(当然取引ナシ)、その時は悔しかったです。でも、店を出て歩きながら思いました。まさにその通りだと、で、その言葉をいただきました(笑)」
・・・
酒が売れないと嘆く社長さんに「情報発信したらいかがですか?」というと、「いや〜、そういうのは苦手で」という人が多いです。どんなにいいお酒をつくっても、伝えなければ存在しないと同じ。お客さんのほとんどは「飲む前に買う」からです。販売店で説明してくれると信じる蔵元もいますが、そんなことは期待薄だと
・・・
最新の桜井さんのメールマガジンで「等外米」について書かれていました。等外米を使用した場合、純米づくりでも「純米」と名乗れません。辨天娘さんの「青ラベル」、諏訪泉さんの「田中農場」、大那さん、志太泉さんなども「等外米」のお酒を出しています。等外米は、量が半端で検査を受けていない米の場合もあります。
等外米について、日本酒好きでもご存知ない方が多いので、桜井さんに許可得て、以下、青字部分、原文ままで紹介します。
読みやすいように一部改行、写真を加えています。
■■■■ 蔵 元 日 記 ■■■■
旭酒造株式会社 http://www.asahishuzo.ne.jp/
2014年4月10日 vol.342
◆ 蔵元日記 【 等外米 】
「カンブリア宮殿」以降、お客さまの反応は大きなものがあります。その上、もしかすると皆様の目に書店などで触れているかもしれませんが、拙著「逆境経営」もダイヤモンド社から発刊となり、反応はさらに増幅されているように感じます。 この蔵元日記を読まれている方にはこの本がこれまでの蔵元日記の抜粋という事はお分かりでしょうが、先日7刷が行われ23,000部を数える事となりました。なんと23千部。23ですよ。二割三分です。駄洒落に喜ぶ私を、周囲のみんなは「あほか」とあきれております。
しかし、そんなおめでたい私の反応は別にして、結果として、お取引酒販店の店頭から「獺祭」が消えてしまっている現実があります。
お客様にご迷惑をかけている現状はどうにもならず、ただただ、皆様のご愛顧とそれに応えられない弊社のふがいなさに頭を垂れるばかりです。(ありがとうございます。そして申し訳ございません)
「こんなときにメディアに嬉しそうに出るな」という酒販店や飲食店様のお叱りを受けることも多いのですが、そもそも、40年間で石数が三分の一になってしまった日本酒業界の現状を考える時、「日本酒ってすごいんだ」「かっこいいものなんだ」という事をアピールしなければいけないと考えています。出しゃばり続けていますが、今少し、ご猶予をお願いします。
とにかく、
「獺祭ってあんなに造ってどうするんだ」(幻の酒にしたくない)
「大量生産で適当に造ってるんだろう」(酒蔵を実際に見に来てください。そして若い社員達の眼を見てください)
「獺祭は酒は美味いが文化がない」(これは少し嬉しい。してやったり)
「獺祭が山田錦を使いすぎるから」(その前に山田錦の産地を見捨て続けた酒造業界の責任はどうするの)
などと非難を浴びながら、獺祭の石数を増やし続けてきました。
しかし、現状の品薄は私どもの歩んできた道が間違っていなかったと確信できるものです。もっとも(印象としては)同じ人から、「そんなに造ってどうする」と「なぜ、こんなに酒がない」と、正反対の二つの非難を浴びているような気がしますが。
そんな話はおいといて、新しい製品を出します。それは「獺祭等外」言葉通り、山田錦の等外米を使用したお酒です。従来、等外米の山田錦を使用すると特定名称表示ができなくなるので、私達には使う事ができませんでした。(もっとも、隠れて使用していた酒蔵もいたらしく、それが最近の偽装表示などで表沙汰になったりしました・・・、灘の大メーカーまで!! うーん!!)
とにかく使わなかったのです。しかし、山田錦を栽培するとき5%から10%程度の等外米は発生するといいます。
私どもは最近、山田錦を栽培した事がない農家にも「山田錦を栽培してください」とお願いしております。これで、一定量出ると予想される等外米を「弊社では買えません」ではあんまりです。これでは「農家にリスクを押し付けるが酒蔵はリスクを取らない」といわれても返す言葉がありません。
そんな理由で山田錦の等外品も今年から購入させていただいて酒を造る事にしました。今年はまだテスト醸造のようなもので750kg仕込み二本と小規模なものです。残念ながら、お取引先に配分するほどの量にならず、ほとんど自家消費のようなものになるかと思います。
ところで、等外米は粒ぞろいが悪いのが特徴ですので、麹は普通の等級付き山田錦の50%精米を使用しましたが、掛け米は等外米のみです。
ちなみに精米歩合は35%まで磨きました。
つまりY・K・35(!!)です。
実は、精米担当のほうからは10%余計に磨くと正規米と同程度という報告は受けていました。つまり、40%まで磨けば50%と同等という事ですね。しかし、それでは面白くないので、さらに5%磨け、と指示して35%まで磨かせたわけです。
勿論、等外米を使用しているわけですから、純米大吟醸表示は無しです。
普通酒という事になりましょうか。このお酒、もしどこかの酒販店の店頭で目にとまったら手に取ってみてください。「作ってもらった山田錦はキチンと美味しい酒に仕上げる」、表示法など色々足枷はあってもお役所感覚でなく本当に社会にとって何が大事か考える。獺祭の新たな一歩です。
山田錦の全国生産総数30万俵を60万俵におしあげて、TPPにも負けない日本の農業を創るお手伝いを獺祭はしたいと思います。
◆蔵元の蛇足◆
農水省のホームページによると、日本の米の総生産数量は8,483,000トンだそうです。すると昨年度の日本酒業界が使用した酒米の総数は24万トンですから約3%弱。そして獺祭が使用した酒米は41,000俵強で2400トン。つまり日本の米の3%が酒米でその1%は獺祭だという事です。
(日本酒の総販売数量に占める獺祭の割合ははるかに小さいのですが、表示上は別として本質的には純米大吟醸だけですから普通の酒蔵の4倍の使用数量がありますから)
何を言いたいかというと、日本の農業がかわる土壌は私達にも少しですが作る事が出来ると考えているという事です。
◎蔵元日記
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000023022/index.html
桜井さんにサインをしてもらうと
「志」! 博志の志!ぷっ!
「逆境経営」
_______________________
【定価を超える「プレミア価格」販売店につきまして】
できましたら、シェアお願いします。
近年、蔵の拡大、そして獺祭の原料となる山田錦の生産農家の方々にも生産量を増やしていただくようにしておりますが、それでも米が足リない状況で、皆様にはご迷惑をおかけしております。
一部、ネットや販売店などで定価よりもずっと高い価格で販売している所が増えていますが、私たちの正規のお取引先は全て定価で販売しており、このような「プレミア価格」などは一切付けておりません。
定価はこちらをご覧ください。
http://asahishuzo.ne.jp/products/items/item.html
正規お取扱店につきましてはこちらをご覧ください。(納品数量を限らせていただいておりますので現在売り切れの場合はご容赦ください)
http://asahishuzo.ne.jp/store/ja/index.html
また、これら正規のお取引先では、冷蔵管理からお客様への説明まで、獺祭をより美味しく飲んでいただくための管理が行き届いていますが、それ以外ではこれらが保障できず、味落ちしている可能性がございます。
美味しい酒を皆様に飲んでいただきたい中、とても辛い状況ですが、ご理解いただけると幸いです。
いつも、ご愛飲どうもありがとうございます。
蔵からのお知らせも追記
↓
【定価を超える「プレミア価格」販売店につきまして】
近年、蔵の拡大、そして獺祭の原料となる山田錦の生産農家の方々にも生産量を増やしていただくようにしておりますが、それでも米が足りない状況で、皆様にはご迷惑をおかけしております。
一部、ネットや販売店などで定価よりもずっと高い価格で販売している所が増えていますが、私たちの正規のお取引先は全て定価で販売しており、このような「プレミア価格」などは一切付けておりません。
定価はこちらをご覧ください。
http://asahishuzo.ne.jp/products/items/item.html
正規お取扱店につきましてはこちらをご覧ください。(納品数量を限らせていただいておりますので現在売り切れの場合はご容赦ください)
http://asahishuzo.ne.jp/store/ja/index.html
また、これら正規のお取引先では、冷蔵管理からお客様への説明まで、獺祭をより美味しく飲んでいただくための管理が行き届いていますが、それ以外ではこれらが保障できず、味落ちしている可能性がございます。美味しい酒を皆様に飲んでいただきたい中、とても辛い状況ですが、ご理解いただけると幸いです。いつも、ご愛飲どうもありがとうございます。
______________________
獺祭さん関連blog
●blog 2013獺祭Store & 獺祭Bar23
●blog 2010近藤さん+musmus+獺祭
●blog 2009獺祭 新酒の会
●blog 2009日本酒を飲む器。獺祭の提案
●鈴木真弓さんblog『獺祭』の躍進と國酒から考える日本の未来–
●【獺祭】ほこたて、で勝利した日本酒蔵元がMLで激しく正しく謝っている
●伝統産業であっても、伝承産業ではいけない革新を追い続けることこそ日本酒の伝統だ 佐藤祐輔新政酒造社長×桜井博志旭酒造社長 対談
「とちぎ酒14」滝田稔さん
April 10, 20144月16日は「新世代栃木の酒・下野杜氏 新酒発表 2014」
http://sasara.lib.net/event/event.html
取材と打ち合わせで栃木へ。大田原市の滝田稔さんを訪問。栃木県が開発した酒米「とちぎ酒14」を初期から取組んだリーダー的生産者さん。家の前庭にはパンジー、ムスカリ、チューリップが咲き始め、幸せを感じる光景
ハウスでは「五百万石」の田植え準備中。
田植えの順番は「五百万石」→「コシヒカリ」→「とちぎ酒14」
稲刈りは、それぞれ8月末〜、9月10日〜、10月7日〜
五百万石の苗。田んぼ430アール分だそうです。滝田さん率いる「酒造好適米研究会」は昨年から1人増えて15人に。昨年は33町歩(ちょうぶ)、今年は40町歩を予定
※1町歩 は 9900 平方メートルで約1ヘクタール。1アール は100 平方メートル
赤土を使用。今月1日に蒔いたという「五百万石」は、初々しいベビーちゃん!
滝田さんいわく「五百万石はスズメの集中攻撃にあう」と。理由は、最初にできること、大粒で見つけやすいこと、 芒(のぎorのげ)がなくて食べやすいこと(とちぎ酒14は芒あり)
「五百万石は穂が横になるので、スズメがとまりやすく、食べやすいかもしれません。他の品種が出ても、五百万石ばかりです」
酒米「ひとごこち」はそんなにやられないそうです。「最後の止め葉が直立しているので、食べにくいかもしれませんね。味の好みが合わないのかもしれませんが(笑)」
滝田さんは家の裏で、椎茸栽培も
椎茸の生育場を見せていただきました。木はクヌギとナラ。
クヌギで育った凛々しい椎茸が、それは美味★ 久しぶりに出会った味のあるおいしい椎茸でした。
クヌギによく菌が定着するものですねえ…とお聞きしたところ、滝田さんニッコリ笑って「普通は無理です。ですが、とあることをすれば(笑顔)」なにやら独自の技があるとのこと。技術が高い人は何をしても上手なのだと痛感。それにしても3年たって、いまだ流通にのせられないとはモッタイナイことよ
椎茸の生育場を見せていただきました。木はクヌギとナラを使用。
なんとも立派な椎茸ですが、基準値を下回ったというのに、風評被害で出荷が難しいそうです。
滝田さんご夫妻
「良かったら差し上げますよ」と滝田さん。喜んで頂戴しました
菌がよくまわると、自然にまたできるのだそうです。
「クヌギによく椎茸菌が定着するものですねえ…」とお聞きしたところ、滝田さんニッコリ笑って「ある手間をかければ、ね(笑顔)」
なにやら独自の技があるようでした。技術が高い人は何をしても上手。
それにしても3年もたって、いまだ流通にのせられないとはモッタイナイことであります。
いただいた椎茸は、凛々しい姿
弾力性も充分!久しぶりに出会ったおいしい椎茸でした。
傘に自然塩パラパラ、太白胡麻油をたら〜りまわしかけて、グリルで焼きました。カリッ、ジュワ〜と、味が濃い〜!
干したり、煮たり、佃煮にしたり、いろいろ楽しんでみます
_________________________
「とちぎ酒14」
炊いて食べたら、甘く、モチっとした食感で、想像以上に炊いておいしい。16日に登場します。それにしても大粒、胚芽もビッグ!
●新世代栃木の酒2014
http://www.yohkoyama.com/archives/61150
静岡県漁業協同組合・女性部大会 魚で肴★ブランドのつくりかた
April 8, 20143月はいろいろな行事が盛り沢山でした! 思い出し記録。
まず、3月6日はグランシップで静岡県漁業協同組合・女性部大会で講演を。担当の川口照恵さんが熱く! 去年から何度も打ち合わせを重ね、気合充分で望みました。
静岡県の茶業農産課・増井裕子さん&平野香理さんも、この会にジョイン。漁連女性部の皆さんに県の優れた純米酒とお茶を知ってもらおうと、女子(決して…子ではありませんが)による、女子のためのパワー炸裂会となりました。
東京・打ち合わせ時のスナップ。手にしているのは地元海産物!(左)川口さんはハバノリ、(右)平野さんはたたみイワシ!
____________
魚価は下がり、魚連女性部員の平均年齢は上がり、会員は減る一方。魚加工品にも力を入れてはいますが、その商品は誰にどう売るかが問題で…。
どうしたら、作りがいがあり、適正価格がキープできる魅力ある商品にするか!であります。
魚は ”誰と組む” かが重要だと思います。
少し前のブログでも紹介しましたが、酒蔵さんが地元素材を、酒と合わせて提案することも大いにあり。魚といったら肴ですから。上質な純米酒と組める魚=肴を目指す!これも、ひとつの方向だと思うのです。
上質同士が手を組んで価値を高める! そのためには互いを知ること。
そんな会を実現しようとあいなりました。
前夜の最終打ち合わせ。会で試飲するお酒のチェックを兼ねて浮月楼浮殿へ。県内のお酒が勢揃い! お店のお酒担当・羽根田陽亮さんの知識も素晴らしいです。お燗温度もバッチリ!
大会は、JAなど、他からのお客様も集合
スタートは女性部代表が大会宣言
来賓の挨拶の中でも、「和食の世界遺産」の話が織り交ぜられ、みな、魚食文化を改めて考えていることがわかります。
さて、今回の講演タイトルは「サカナ×発酵×酒米誉富士 プレミアムな酒肴は静岡の海から!魚で肴★ブランドのつくりかた」です。(ちょっと長い…。セミナー中の写真は漁連さんから拝借)
魚連の熱血!川口さんが冊子も製作
なぜ、地元の上質の純米酒と組むのか、その重要性をお伝えしたいと、用意したパワーポイントは100枚以上!
↓農林水産省affで連載した水産関連の記事も冊子に
板わかめ
しょっから
ぬかいわし
しょっつる
紅ズワイガニ
セミナー終了後、試飲試食timeへ
ただ話を聴くだけではなく、体感してもらうのが大事。県外の参考事例や、県内の食品、県内の純米酒とお茶を試飲
静岡県オリジナル酒米・誉富士の純米酒に、魚介類を使った発酵珍味各種
イカの塩辛・赤づくり、白づくり、イカの三升漬け、イカの麹漬け、イワシの糠漬け、おやつ煮干し、炙り板わかめ、ジャコを使ったジャコロッケなどなど。添加物を使ってないことも重要です
そしてこちらは、女性部員が手作りした「つめた貝の佃煮風」
つめた貝!嫌われ者と聞いてましたが 、においが強烈とも聞いてましたが 恐る恐る食べてみると!なかなか風味が良かったです。
____________________
その肴はどんなお酒に合うのか。純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸……ひとくちにお酒といっても様々。そして温度もいろいろ楽しめるのがいいところ。「あの蔵のあの酒に合う!をイメージして作った〜♡」といわれたら、試したくなりますよね。それが言えるような商品作りが大事!
それは、誰に、どんな風に食べてほしいの?
____________________
●静岡の酒
静岡県は「吟醸王国」といわれ、特定名称酒比率が高いことで知られています。
ですが、県民は・・・あまり、知りません。飲んでません。
吟醸比率は全国平均28.1%のところ、静岡は82.9%!
全国平均の3倍!
というわけで、女性部の皆さんにこそ、その上質な味を知ってもらおうと
お出した酒は、静岡オリジナルの酒米・誉富士の純米酒
静岡生まれ静岡育ち
さあ、飲んでみましょう〜
●白隠正宗 誉富士純米酒 高嶋酒造
沼津市原
●正雪 誉富士辛口純米 神沢川酒造
静岡市清水区由比
●杉錦 誉富士山廃純米 杉井酒造
藤枝市小石川
同時に、お茶もサービスです。掛川の「深蒸茶」と「静岡型発酵茶」(花様、果実様の香りが強く、健康志向にマッチする機能性成分を含む開発中の茶)。お茶振興班のスタッフがテキパキとサービス!
「深蒸茶」は茶草場農法http://kakegawa-kankou.com/chagusaba/
(左)深蒸茶 (右)静岡型発酵茶
・
皆さんにお酒の感想を聞いてみました
「思ったより飲みやすいです。フルーティで爽やか、するするって(笑)飲めました」
「いつものと違いますね」「ええ、おいしい(笑)」
実際に食べてみる、飲んでみるとナルホド!という気づきが多かったようです。皆さんのコメントも活発で、帰りがけには「来てよかった!発想がふくらみました!」という声も。
「ふじのくに静岡県は和食の先進県」
今、求められるのは、光景が浮かぶ食。お酒なら、お米の名前が言える純米酒。田んぼで成長が見守ることができる地元のお米。
土地と造り手の顔が浮かぶのが最高です。
地元の純米酒を飲むことで、田んぼ、環境、水系、杉山、器を含む日本の伝統産業も守られます。
いい純米酒にあうのは、いい発酵食。
魚介×発酵=上質な加工品ができれば、魚食文化が価値付けされて、互いの魅力を倍増。
魚を肴として価値付けし、海の幸を☆がつくブランドに育てたい!
元気が良い桜海老の産地・由比のメンバー。「私たちの町には酒蔵があります!一緒に考えたい」と嬉しい言葉が聞けました。
住む土地の酒米でつくられた純米酒を飲むことは、その土地を守ることにつながります。
地域は一人一人が選択する「食」が支えています。
その動きは町から県、日本もと信じています。
川口さん、増井さん、平野さん頼もしいチーム静岡です。
___________________
翌日、川口さんから届いたメール
↓ ↓
山本洋子さま
静岡県漁連川口です
昨日は、大変お世話になりました
どうもありがとうございました
何かと不備な部分もございましたが
終りよければすべて良しで、お許しを願います。
すごく楽しかったです。
すごく大変だったです。
講演会?パーティー?大会?もう何でもいいや!えいっ!!てやっちゃいました
参加者には印象に残る大会になったようです。
事務局冥利に尽きます。
これをきっかけに、「なにか」発展しそうな予感がしています
とりあえずは、由比で
増井さんたち茶業農産課の方たちの宣伝方法も、勉強になりました
漁業は、生産者も私たちみたいな、漁業団体も、もっともっと宣伝しなくてはと思いました。
それから、私たち漁業関係者は研修会や講演は当然、漁業に関係する内容ばかりです。
だから、私は今回のお酒やお茶の話は、初めて聞くことが多く、すごく新鮮で、知ったかぶって、まわりに話したくなってしまい、やたら「誉富士」の宣伝していました。
宣伝料もらってないのに(昨日残ったお酒もらっちゃったけど)勝手に宣伝してた。増井マジックにはまった!!
てことは…漁業に関係ない人たちは、漁業の話聞いたら私たち以上に吸収してくれて興味深いってこと?
しかも、団体の集まりだと、それなりに意識の高い人が集まるし、研修会慣れしているから、一層新鮮てこと?
確かに増井さんも魚のことすごく興味あったし、過去に農協の研修会で事例発表したり一緒に魚料理教室やったとき、一般の方対象のときよりもすごく反応がよかったことを思い出しました。
山本さんがおっしゃっていた、酒蔵⇒酒販店⇒旅館・料理店ルートってまさしくこれだ。と、
漁業関係者以外の意識の高い人達の集まりで宣伝することが、もっと必要なのだと、さんざんお話きいていたのに、今さら実感した次第です。
「静岡の誉富士純米酒には静岡の魚で肴」
今後ともよろしくお願いします
再会の日が楽しみです。
くれぐれもお身体ご自愛くださいませ
純米酒と魚で健康保持を身をもって伝えてくださいませ
**********************************
静岡県漁業協同組合連合会
指導部 漁業振興課 川口照恵
・・・
去年から綿密に打ち合わせを重ねて、準備し、やりがいのある仕事でした! 嬉しかったので本人の許可得て原文ママで紹介
見上げて楽しい桜飲み
April 6, 2014桜咲く
平和な時間に感謝
お友達のバッグ、開けるとボトルがぎっしり
でした(笑) よくまあこんなに担いできたなあと感心
橋のたもとで瓶を並べると「お店やさんみたい〜」と声をかけられたり、笑われたり(ぷっ)
ハラハラ落ちた花びら浮かべて楽しんだり
隣でワインを飲んでいたお二人が、日本酒群に興味をもたれたのでおすすめしました 全種類制覇していただき、とってもうけてHappy! それぞれのお酒のコメントがなかなか的確でナルホドでした。
中でも、好きなお酒の評価が高くて嬉しかったです。おいしいお酒は共通かな
幸せそうに飲んでいると寄ってくる!?ことがわかりました(笑)
おつまみは、玄米小豆ご飯、青菜のおひたし、わさび菜のナムル、沢庵、蕪、ミニトマト、味噌、梅干、能登の海苔、能登のカワハギいしる漬け。アルミホイルの中身はイワシの塩焼きとししゃも焼き!
久々にアウトドア用品も活躍! 日置桜の鍛造にごり、白隠正宗のお燗を楽しみました〜
違う場所に移って別の桜ウォッチング。ソメイヨシノの寿命を考えたり
合間に喉が渇いたので、オーガニックの泡も
するとお隣さんグループに声をかけられ「ワイン抜きお借りできないでしょうか」
持っていなかったので↓この方法を伝授「え〜! 靴で(笑)」
https://www.youtube.com/watch?v=u1wROm-OF9w#t=34
http://matome.naver.jp/odai/2138599226538767201
やってみましょう〜と、皆なで代わりばんこに底を打ち付け、しばらくするとコルクが上昇!
「開いた〜〜!」喜びの図
不安そうに見ていたご家族も大喜び!
お礼にそのワインをいただき、日本酒で返杯
よかったよかった。「お酒、おいしいっすね!」
常温もいいし、お燗はしみじみおいしい、間の泡もよござんしたが
青空の下、満開の桜と日本のお米のお酒♡
笑顔で飲めるって、なんて幸せなことなのかな〜
カメラ RICOH GR
________________________
●ソメイヨシノはクローン品種
http://satoshi.blogs.com/life/2005/04/post_7.html
●ソメイヨシノ 雑学
http://www.rcc.ricoh-japan.co.jp/rcc/breaktime/untiku/080325.html
http://nihonsakurakikou.sakura.ne.jp/gosikizakura1.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%A9
若手の夜明け2014
April 3, 2014↑ROCKETNEWS24
20140330は「若手の夜明け」に参加!年々素晴らしい成長をとげる若き蔵元たちの自主企画
●ROCKETNEWS24【日本酒】いま『若手蔵元』がアツい! 若き日本酒マイスターたちの創る美味しい日本酒を求める人たちでイベントは大盛況
●
動画もあり ↓ 会の雰囲気がよくわかります
【酒蔵PRESS】第14回 若手の夜明け「銘柄紹介 前編」
【酒蔵PRESS】第14回 若手の夜明け「銘柄紹介 後編」
【酒蔵PRESS】さんが『若手の夜明け』の動画を作っていただきました。
こちらは「会場編」
【酒蔵PRESS】第14回 若手の夜明け「会場編」
●
毎回、一部、二部、三部と分かれて開催され、最後の三部は蔵元セレクトのおつまみ付き!そして蔵元も飲むということで、にぎやかに盛り上がります。
静岡の白隠正宗さんのおつまみは、これまでは鰹の塩辛でしたが、今回は前々回のブログでUPしたコチラ↓
「なまり節+金山寺みそ=酒肴」
これが素晴らしい一品!地域の特徴も出ますし、何より白隠正宗のお酒にあうあうあう!
今回、秋田で一白水成を醸す渡邉康衛さんが、地元五城目町産のキイチゴを使うというのでお手伝いしました。
きれいで品のいい甘みと酸が特徴の「一白水成」の味に合わせたキイチゴつまみ
そのままでは酸っぱいキイチゴですが、お酒に5分ほどつけると、香りと酸味がうつって美味♥これもいいなあ〜と思いましたが、提供時間が微妙。おつまみでもありませんし、そこでキイチゴを贅沢に使ったpink色のクリームを作ることに
名づけて
framboise de koei crème
↑説明カードも作成。キイチゴをフランス語のフランボワーズで紹介(ちなみに英語だとラズベリーです)
” framboise de koei 一白水成の蔵がある秋田県・五城目町産のキイチゴを使った framboise de koei crème お酒と合わせてお楽しみ下さい “
原材料=五城目町キイチゴ、クリームチーズ、カマンベールチーズ、とろとろの純米大吟醸酒粕、はちみつ and more
↑クリームはもちろん、無着色です。一粒のせて提供
「うわ〜!かわいい♡ おいしい〜」と喜ばれました。渡邉さんの雰囲気にもピッタリ(笑)
秋田という北の地で栽培されるキイチゴと日本酒に興味を持ってもらえたようです。国産キイチゴは珍しいですからね。
その土地の、上質な酒と上質の素材が組み合わさると、その土地の魅力がさらにUPします!
五城目町には500年続く朝市もあり。いってたんせ〜。日帰りおすすめ旅プラン
_____________________
●キイチゴの研究と産地形成
●国産ラズベリーの市場創出に向けて
_____________________
●過去の若手の夜明けhttp://www.yohkoyama.com/ archives/47785http://www.yohkoyama.com/ archives/47824http://www.yohkoyama.com/archives/17769http://www.yohkoyama.com/archives/695
新世代栃木の酒・下野杜氏 新酒発表 2014
April 3, 2014日本酒セミナーを担当します(^^ゞ
栃木県は鹿沼土をはじめ上質な「土」で知られる土地であります。
新世代の下野杜氏は以前より、こぞって県産米、県酵母を使用した酒づくりで、土地の個性、自らの設計を表現しています。
・
なのですが、栃木の酒米そのももの魅力、底力がどのようなものなのか、県外の人間には、あまり伝わってこなかったのも事実。
・
今回のセミナーでは、酒米名人・滝田さんに伺った土の話(沖積土、黒土、赤土の差)をはじめ、栃木オリジナルの酒米「とちぎ酒14」をじっさいに食べて味わってみようという(酒米不足なのに…)という大胆企画!
・
よくよく噛んで味わったら、次には勿論!醸された液体=酒ですよ〜!をゴクリ!あの酒米が酒蔵でこう変わる!?が体感できる、栃木の酒がよくわかる絶好のチャンスです★ セミナーは入場無料で予約不要なのですが、人数制限ありなので要注意。
4月16日水曜日・栃木の27蔵の新酒試飲会があります。
日本酒セミナーを担当します
栃木県は鹿沼土をはじめ上質な「土」産地でも知られています。
新世代の下野杜氏は以前より、こぞって県産米、県酵母を使用した酒づくりで、土地の個性、自らの設計を表現してきました。
あの蔵元に会える!
なのですが、栃木の酒米そのももの魅力、底力がどのようなものなのか、県外の人間には、あまり伝わってこなかったのも事実。
今回のセミナーでは、酒米名人・滝田さんに伺った土の話(沖積土、黒土、赤土の差)をはじめ、栃木オリジナルの酒米「とちぎ酒14」をじっさいに食べて味わってみようという(酒米不足なのに…)という大胆企画!
よくよく噛んで味わったら、次には勿論!醸された液体=酒ですよ〜!をゴクリ!あの酒米が酒蔵でこう変わる!?が体感できる、栃木の酒がよくわかる絶好のチャンスです★ セミナーは入場無料で予約不要ですが、人数制限ありなので要注意。
●チケットはe+で↓受付が本日18時まで
http://eplus.jp/sys/T1U89P0101P006001P0050001P002119747P0030001P0006
ご紹介の蔵元は超一部!参加蔵元は全部で27蔵です。お楽しみに( ♥ᴗ♥ )
●blog 前取材その1↓
http://www.yohkoyama.com/archives/61150