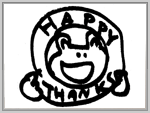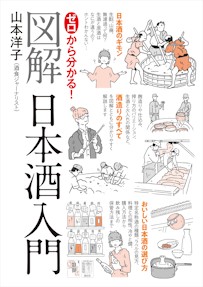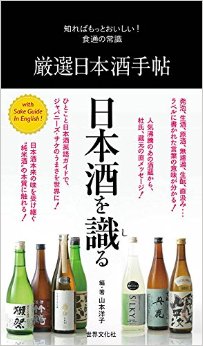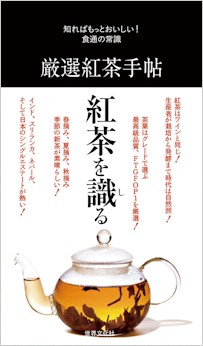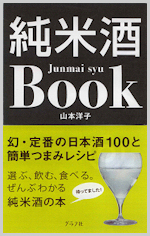日本酒
« Previous Entries Next Entries »境港で紅蟹三昧!蒸し&坊主殺し
May 10, 2013紅ガニつづき。そして!「蒸し」
新鮮な生蟹を蒸す。これが繊細なカニの甘さがよくわかります。きれいな味わい。
身の色が白くふっくら仕上がって、これまた美味。これだけで味が完成されているので、調味料はまったく不要!
泡が進みます〜。(右)川口さんセレクトの「地ウニ」! 島根半島産でふるふるっとした舌ざわり、品のいい甘さとうまみ。これにあうお酒ってなんだろう。
こちらの出番かな!
蟹の甲羅はひとり2つずつ
ひとつは味噌、蟹味噌〜!
そしてもうひとつは出汁を味わう具なしの茶碗蒸しプルプル。茶碗じゃないから「甲羅蒸し」ですね
そして隠岐島産、春が旬の岩牡蠣です。海そのものを味わうようなクリーミィでミネラリー、ぷるぷるんとした弾力
こちらはお造り。サヨリ、猛者(もさ)エビ、鯛、マルゴ(ブリとハマチの中間) 、アジ。
そして、初めて食べた海藻! 真っ黒クロスケでツヤぴか
「バーズゴロシです」と川口さん。バーズ!?
随分、ブッソウな名前がついた海藻「坊主殺し」とは↓さてはて
http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/646640/sakana100sen-80.pdf
なるほど!葬式が減って…坊主いらず。医者いらずじゃなくて、坊主いらずと。なになに食べ過ぎ坊主説も!?
今が旬の海藻「坊主殺し」(ネイティブは「ボーズ」ではなく「バーズ」と発音)風味も食感も抜群の季節のごちそう。まだまだ知らない日本海の幸がいっぱいです!
緑は山葵、オレンジ色の薬味は地元ウニ、針ネギ、そば出汁だそうです。凝ってます。
蟹とお酒が進んで、ベニガニ川口さん脱皮。すると新たな蟹仲間が増え、お酒を注ぐの図。
サインはVでも、ピースでもなく、蟹の手足を表現(らしい)
そして、川口さんが立ち上がった! 甲羅を持って!
王祿の「丈径」をトクトクと注ぐ
甲羅違いで注ぎ分けです。「焼き」と「蒸し」だと甲羅の風味、みそ味がまるで違い別の甲羅酒になります。
おいし〜っ!!
感激して隣の石原丈径(蔵元杜氏)さんに伝えると、目を細めてポツリ「そんないい酒を…あたりまえだがね」
「丈径(たけみち)」という酒は本人の名前をつけたほどのコダワリ酒。地元契約農家に委託した無農薬無肥料栽培の山田錦を使った純米吟醸酒。しかも、ひとタンクで数本しかとれない貴重な「直汲み」。おいしいのはアタリマエ。つくり手から言えば、甲羅酒にするには「もったいない…… 」
そのおかげでありえないほどうまい!蟹のブイヤベースかコンソメか。いや、もうおいしかったですわ。酒はいいものに限る。
宴たけなわ、料理も出し終えた美佐のオーナー料理長・濱野さん登場! 蟹ポーズでパチリ。もうお約束です。濱野さんは境港の魚食文化振興のため子供向けの料理教室をしたり、境港ベニガニ有志の会の会長をつとめ、境港ベニズワイガニ推進協議会の活動もがんばっておられます。濱野さんの想い(一部)
まずは「丈径」を一盃!
そして「王祿」も一盃!ありがとうございました
赤ワインも登場。最後は蟹雑炊!
いつのまにか蟹さんが増えて2人+脱皮中の人。そうこうするうち脱皮蟹さんからbodyの蟹Tシャツが奪われ
嬉しそうに着てる人がいて全員で記念撮影。最後にシャンシャンと〆!ごちそうさまでした
お茶をいただいたら! 甘く香ばしい茶色のお茶。蓋を開けてみるとやっぱり!「浜茶」でした カワラケツメイをブレンドしたお茶でこの地域ならではのもの。濱野さんのセンス、最後まで素敵だな〜と思いました。地の料理には地のお茶がピッタリです。
最終の境線で帰る田村さんと順子さん。電化されておらず電車ではなく列車です。目玉おやじに鬼太郎ねずみ男もありますが「ねこ娘」列車でした。さよ〜なら〜。二晩ありがとう!
おいしいは幸せだなあとあらためて。
いい人が原料から選んでつくるおいしいは幸せもイッパイつくります。おいしいイッパイ、蟹イッパイ、それに合わせたお酒もイッパイの紅蟹三昧ナイト★ 皆さまありがとうございました
●SAKE 王祿
丈径直汲 23BY
王祿純吟限定生原酒 23BY
●WINE マヴィ
Eugen Meyer クレマンダルザス Brut
Diwald ツヴァイゲルト&ポルトギーザー ロゼ (1L)
Eugen Meyer クレマンダルザス Brut (2本目)
Diwald グリューナーフェルトリーナー白
Chovin アンジュ白
Eugen Meyer アルザスピノノワール 赤
______________________________
●境港のベニズワイガニ
●川口さんの直営店 http://kani.ocnk.net/
●味処 美佐さん http://www17.ocn.ne.jp/~kuimono/
●美佐・濱野さんブログ http://ajidokoromisa.blog.ocn.ne.jp/blog/
やまよ蟹
蟹カブリの生地が意外にソフトで温か。顔にしっくりなじんでいい感じでした(笑)つけてる顔、その時は自分じゃ見ませんが〜っ
しち十二候で秋田 新政の会 後編
April 22, 201320130419(金曜日) 末候 第十五候 虹始見
六本木三丁目・しち十二候・ソムリエの小栗さんです。
テーブル・セッティング
会宴前、お酒のセラー前にて。提供する順番を確認中
新政酒造の佐藤祐輔社長と酒屋・水橋の水橋信也さん。お酒のセラー
No.6 S-type 生酒、No.6 R-type 生酒。出番待ちの手吹きグラス。影がかわいい!
斎藤章雄料理長です。 しち十二候オリジナルの手吹きグラスを手に。
今宵のラインナップ!
挨拶する斎藤料理長。まず乾杯はフロスティグラスのような白いお酒が注がれました。
「霞発泡生酒」です。右)「筍 木の芽和え」爽やかな一品
左)前菜はひとつ前のブログを。右)御椀は「しょっつる仕立て」はたはたがそれは上品な一椀に。しょっつるは諸井醸造製。
造里「ボタン海老、鰹たたき、鯛、あしらえ色々」
熱く語る祐輔氏。新政酒造は秋田県の米しか使わず、全量純米酒。そして酵母は協会最古の現役酵母である6号のみ。新政酒造で発見された6号酵母、発祥蔵なのです。
凌ぎ「鱚昆布〆 手巻き寿司」
斎藤料理長のスペシャリテ「焼き胡麻豆富 天、生姜」! カカオのような香ばしさと品のいいコクと甘さが絶品。
こちらは「頒布会限定 白麹菌の純米酒」
焼物は「味噌かやき」。強肴は「松葉独活(アスパラガス)の豆乳酢かけ」
そして「きりたんぽ鍋」登場! 具はたんぽ、比内地鶏、舞茸、葱、牛蒡、芹、薄揚
斎藤料理長のきりたんぽ初めてです!
最後には「稲庭うどん」。デザートは蕨餅です。
斎藤料理長の手にかかると「秋田」がそうなる!をたっぷり堪能。
●新政酒造ラインナップ
左から、霞発泡生酒
No.6 S-type 生酒 No.6 R-type 生酒
頒布会 白麹菌の純米酒/青やまユ 生酒/鑑評会出品酒(ノーラベル)
祐輔さんのLove Letterとも言われる裏ラベル
↑日本酒度、酸度に注目
微炭酸!気持ちよいシュワ感。米粒はありません。スムーズ!
No.6 S-type 50%
No.6 R-type 60%
斎藤章雄料理長と佐藤祐輔社長
最後に記念撮影パチリ★
◯新政酒造・佐藤祐輔社長のblog
◯六本木三丁目・しち十二候=斎藤章雄料理長のblog
しち十二候の料理コース →スゴワザ満載のマクロビオティック料理もおすすめです!
しち十二候で秋田 新政の会 前菜
April 21, 2013末候 第十五候 虹始見(にじ、はじめてあらわれる)雨のとき虹を見る時季。
斎藤章雄料理長の店六本木・しち十二候で「秋田 新政の会」が開催されました。
料理には秋田食材が散りばめられて登場。
前菜には「いぶりがっこ蒸し湯葉 、なた漬け、はたはた骨煎餅、はたはたいずし、桜エビ、焼き蚕豆、新じゃが、蒸し比内地鶏」が。
秋田素材が斎藤料理長の手にかかるとそうなる!を満喫しました。
お酒も勿論オモシロし★
●新政ラインナップ
霞発泡生酒
No.6 S-type 生酒
No.6 R-type 生酒
頒布会 白麹菌の純米酒
青やまユ 生酒
鑑評会出品酒
◯新政酒造・佐藤祐輔社長のblog
◯六本木三丁目・しち十二候=斎藤章雄料理長のblog
つづく
_______________________
斎藤料理長関連ブログ
●blog 丸の内一丁目 しち十二候で野菜ランチ
201003blog齋藤料理長さよならコンラッド
201003blog料理長さよならコンラッドno.2
201003blog料理長さよならコンラッドno.3
鰤寒干し2ヶ月半熟成ぶらぶら!富山at丸の内
April 18, 20132013年4月10日から21日まで富山県主催「おいしい富山のつくりかた 五感で味わう富山の秘密」を丸の内ハウスで開催中
17日はmus musでレセプション。石井隆一知事の富山魅力語り
「富山県産の錫の酒器で飲むとお酒が格別に美味しくなる」など富山の美味しいを盛り込んだトーク
富山大好きの文筆家・白洲信哉さんのトークも。蛍烏賊は富山県産に限ると(蛍烏賊は酢味噌じゃダメ、生姜醤油おすすめ)。また「梅雨マグロ(自称)」は最高に美味しいという(大間のマグロは目じゃないと)そして風の盆は凄いなどなど。
そして今宵!
あの!富山珠玉の居酒屋、あら川&米清・店主の荒川数夫さんがこのイベントのために上京。久しぶりの再会となりました
持参したのは
ド迫力!鰤の寒干し2ヶ月半熟成!!!荒川さん自らが仕込んだ情熱の発酵食品です。
「鰤の寒干し・二ヶ月半熟成」を包丁持参で裁いてくれました。上質の鰤を刺身ではなくあえて発酵食品に。本人いわく「趣味の一品です」★★★
だんだんスリムになる鰤寒干し。生ハムがぶらさがっている店はあっても、鰤寒干しが下がっている店はなかなかないでしょう。
この鰤寒干し、部位によって味が違いました。
そして、粗挽き黒胡椒をふったらあうあうあう! うま味にエッジが立つ感じ。
その他の部位も珍味度合い深し。カマを焼いたものも絶品でした。
富山県の日本酒もズラリ!
そして各店舗が腕をふるった富山素材の料理
白エビ!
「生」かまぼこのしゃぶしゃぶ〜
蟹にホタルイカ
白エビかき玉丼に白エビのアヒージョ
富山県は昆布県。おむすびの昆布は黒と白
柿太水産の一夜干しイカに、ゴロ入り干しイカにメザシ〜
これは蒲鉾の新スタイル「ボコちゃん!」だとか。おーっ
最後の最後の、解体ショー!いながらにして富山が味わえた夜。
鰤寒の最後の図。
北陸新幹線が開通すると東京から2時間7分で行けるそうです。早っ! 飛行機ピンチ?
・
●荒川数夫さんの店に行った時のこと↓
2009bog http://www.yohkoyama.com/archives/2720
2012blog http://www.yohkoyama.com/archives/42671
2012blog http://www.yohkoyama.com/archives/42697
・
撮影 RICOH GXR A16 24mm-85mm
純米酒蔵の麹セット
April 15, 2013ALL純米酒蔵「杜の蔵」から新しい食ブランド「百福蔵(ひゃくふくら)」がデビュー。
「純米酒蔵の米麹」お米は酒米・夢一献を使用
まぶしい白さの米麹☆
「純米酒づくりの贅沢塩麹」
なにが贅沢かって、塩麹に純米酒を使用! ツヤあり、とろり〜んとしています。
百福蔵の麹と塩麹は、味のきれいさが魅力。杜の蔵の吟醸酒を思い出します。
「琥珀の料理酒」料理酒なのに山田錦!しかも農薬不使用栽培の糸島産・山田錦、これを熟成酒粕四段で仕込んでいます。某吉祥寺の人気日本酒店でも提供!?している飲んで美味しい料理酒。鼈甲飴みたいな色と豊かな酸味とコクたっぷり。お燗がおすすめ。
そのヘンのスーパーで売ってる麹や塩麹、料理酒とは月とスッポンポン☆
麹造りの超プロ末永杜氏が担当しているというので当たり前かもしれません。
麹も上質な米ありき、そして醸す技術なのだと思います。
「麹モノを試したいけど…」というSake好きの女友達にプレゼント。 清潔感あるパッケージと少量サイズがgiftにいいね!
●百福蔵
レシピを紹介しています!
●blog 2012 杜の蔵さなぼり焼酎
思いやりの酒器
April 9, 2013酒器で心が熱くなった話です。色あいが素敵なこの器は、名張の醍醐・福嶋章男さんに教えていただいた逸品。
福嶋章男さんです! 笑顔が素敵な優しい方、料理もうまし!
●blog 名張の醍醐 訪問記 with きもとのどぶ
盃を載せるための台。湖の底をのぞくような爽やかブルーの五角形です。そこに盃をちょこんと載せて使います。
じつはこの器、目が不自由な方のために考えられたもの。普通の盃だと、いったん置いた盃を探す時、手がぶつかってこぼしてしまうことがあるそうです。台に手を当てれば、自然に位置の確認ができます。
位置を確認し、五角形の台に添って盃に触れば、下からすっとそのまま安定して持つことができ、こぼす心配はありません。安心していただくことができます。
すてきな思いやりの心と技に感動。
この器でお燗酒をいただくたびに、多くのことを学ばせてもらっています。
SHIKKI de SHUKI 2013
April 8, 2013漆器の酒器は口当たり温か。寒い地方は陶器よりも漆器が多かったのも納得です。色合いも朱色や溜色など、日本ならではの深い色使いがいい味を出します。朱色の漆の器に、にごり酒を注ぐと景色が最高になります。
そんな漆器ですが、お酒の味が明確になるかどうかは…わかりませんでした。まあ、無難でいい人ね…という感じ。
内堀法孝さんに誘われてアクシスギャラリーで開催の「SHIKKI de SHUKI 2013酒好きデザイナーによる器展」に行った時のこと。
会の主旨は→ 「本展は酒好きが自らのためにオリジナルの酒器をつくり、好みの酒を楽しみたい」という単純な動機から開催される展覧会です。複雑化するモノづくりのプロセスに対して、もっと素直なモノづくりをしたいという想いから、職人とのコラボレーションを通じ「想い」をカタチにすることができました。信州・塩尻市内の三酒造の協力により、試飲による器体験も可能」 という実践的な酒器展!
器がお試し放題! 「見て、触れて、味わえる」展示されている酒器に本物の!?お酒を注いで試せる体験型の展示会。わかったのはデザインの重要性!器は使ってみなくちゃわからない
↑内堀法孝さんです! デザインしたのはこの器↑画像ではよくわかりませんが、円筒型で蟻地獄!?のようにストンと落ちているのです。
内堀さん、じつは時計のデザイナー
地元の若手漆器職人さんとコラボ★
「kakumaru」
デザイン:内堀法孝
漆器制作:伊藤寛司商店、木曽漆工、未空うるし工芸、丸嘉小坂漆器店
内堀さんデザインの酒器、色は3種類。唇があたる部分は極薄で、そこからグッと下がる(蟻地獄)のような形。さて、どんな味わいになるのか?想像つきません。
(左)表面張力ギリギリまで注いでみました。(右)タッグを組んだ若手職人の岩原さん、升とトレーを担当。
内堀さんのコンセプトはカクマル!
●このblogに詳しい解説あり→kakumaru
↑なのだそうです。昨年は「1日1合」で枡のタイプを作製。それじゃ量が足りないと・・・
片口と器。カクとマル=カクマル
その他にも様々なデザイナーが考えた酒器がズラリと並びました。これが試せるのが嬉しい!
そしてお料理も漆器の皿に
漆器に並べられたフード。かわいい系のおつまみだと思ったら、女子大生の作。昭和女子大学環境デザイン学科の生徒さんが担当されたそうです。
スタッフ披露コーナー。右が女子大生ズラズラ、日本酒はほとんど飲まないという。これから飲んでください
初めていただいた美寿々酒造さんの美寿々・純米吟醸 美山錦 無濾過生
他、笑亀酒造さん、 丸永酒造場さんのお酒も。蔵元さんからひとことずつ
さて、実際、内堀さんの器で飲んでみました。一緒にいった浅井直子さんと試した感想は!「おいしくなる(驚)」
意外なことに、お酒の欠点を消し、きれい系の味にチェンジ。いや、予想外に(内堀さんスミマセン)おいしくなったことにビックリでした。狭めの口径と口が当たる部分の極薄形状これがキモかもしれません。飲んでみなくちゃわからない〜
こういう体験型の展示会はいいですね。
見ただけではわからない味わいの違いがその場でくっきり!よくわかります。酒器は味わってナンボ。漆器もデザイン次第!を痛感しました。
SHIKKI de SHUKI 2013関連blog
●jiku AXIS Magazine
●ここから、
●facebook Shikki de Shuki
日本酒の器に思う
April 2, 2013↑リーデルの大吟醸グラス(画像はリーデルから許可得て拝借)
常日頃、日本酒を飲むにあたり重要だと感じるのは「器」です。
日本酒ほど酒器の素材と形にバラエティがあるお酒は、他にありません。
素材は磁器、陶器、硝子、漆、錫、杉と様々。
形も、ぐい呑み、平盃、猪口、枡と、色形ともにバラエティに富んでいます。
器次第で味わいがガラリと違うので、家では1つのお酒をいろいろな酒器で飲み変えて楽しんでいます。
↑我が家の酒器引き出し。グラス類は別に収納。どれで味わうか見てるだけで楽しい!
ワイングラスといってもさまざま。味がそれぞれに異なります。
・
苦手なのは「こぼし酒」です。
あれほど酒の味をマズくするものはありません。手がベタベタし、しずくがたれて服に落ち、ろくな展開になりません。前屈みになる姿勢もどうかと。
また、器がちゃんと洗われているのか不安。秋田杉の新品の枡なら意味合いも違ってきますが、こぼし酒に使われる枡はほとんどが漆器風。そこにミニグラスを入れるパターン多し。枡の四隅きちんと洗ってる?グラスの底洗ってる?さっきテーブルに置いてなかった? 不安がいっぱい。こぼれた部分の酒のマズさったら。丁寧につくられたお酒に失礼極まりなし!
繊細で美しいデリケートな味の日本酒だからこそ、最高においしい状態で大切に飲みたいもの。というわけで、こぼし酒撲滅運動(ひとり)展開中です。
世界でもっとも使われている酒器といえば、なんといってもワイングラス。
そのワイングラスに注いだ時においしいお酒ってどんなタイプ?
それを問うのが「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」
●2011年に審査員で参加→ワイングラスで日本酒を・WGOアワード2011
グラスで飲むと、お酒の微妙な色や粘度、香り、長所と短所も明確になります。
着々と増えている海外での日本酒。
世界中のレストランで飲まれる日も遠くない今、改めて日本酒をワイングラスで飲むことについて、考えるきっかけになる審査でした。
酒文化研究所の山田聡昭さんいわく「今年は入賞酒試飲パーティあり」と。4月22日に六本木ヒルズで開催だそうです。
ここで使われるグラスは、リーデルの「大吟醸グラス」足のないタイプ http://shop.riedel.co.jp/riedel/a-a/414-22.html
これに見合うお酒なのか、どうなのか。酒蔵が選んだグラス向きのお酒を確かめるチャンス
◎「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」
会費は3000円
自分が使ったリーデルの大吟醸グラスはそのまま持ち帰りも可。その味わいを自宅でも楽しめるという趣向。へ〜っですね。
お申し込みはこちら↓から。
https://www.s-db.jp/entry?k=74f2f0701851bedd16883451be2395c0747%2CeI
●会詳細↓
http://www.finesakeawards.jp/2013/awards2013.html
●blog 2009年8月「日本酒を飲む器。獺祭の提案」
春のにがみ
March 25, 2013センスいいな〜と思った「春のにがみ」セット。この季節の酒肴としてピッタリ。
色合いにもそそられました。
白隠正宗蔵元杜氏・高嶋一孝さんのgood★チョイス
食は人柄がでますね!
カネコ小兵さんの一献盃
March 23, 2013カネコ小兵製陶所の「一献盃」シリーズに、待望の小さいハーフサイズ(約60ml)が出ました!
詳細は→http://www.ko-hyo.com/konpai.html
それぞれ違う型、ストレート型、ラッパ型、ワングリ型、ツボミ型と4種類。同じお酒を注いで飲んでみるとまるで味わいが異なるのです。
「いいお酒の器はみんなグラスでしょう。悔しいですよ」と以前、カネコ小兵の伊藤克紀さんがおっしゃっていたことを思い出しました。
カネコ小兵さん、技術力が高くこんな器もありました↓
●blog ホワイトビスクの極薄カップ
いや〜っ、日本酒の楽しみがまた増えましたよヽ(^。^)ノ
今、開発中という正一合のとっくり片口も興味津々です。
そもそも、カネコ小兵さんのお得意はとっくり
その最盛期は昭和40年代後半
カネコ小兵さんだけで月に13万本! 製造していたそうです。いや驚きました。
詳しくはこのブログ↓を
●bog 2009 岐阜 カネコ小兵さん訪問記その2
« Previous Entries Next Entries »