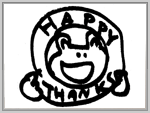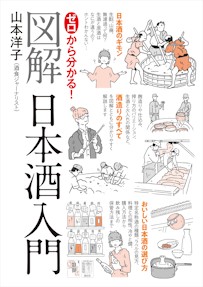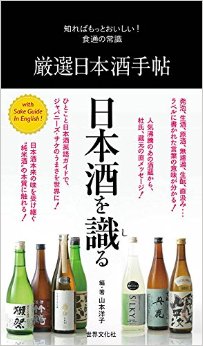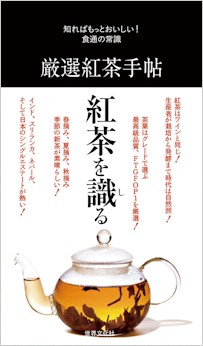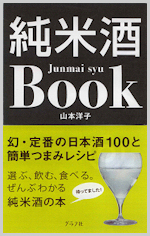shop
« Previous Entries Next Entries »島根 出西生姜の生姜糖
December 6, 200711月に落語つき山陰ツアーに出かけたときのこと。「來間屋生姜糖本舗」さんへお邪魔することができました。生姜糖は伊勢神宮をはじめ全国の神社仏閣土産として昔からありますが、ここ來間屋生姜糖本舗さんは創業300年、ひたすら生姜糖1本!という潔さ。
原料の生姜は、島根県簸川郡斐川町出西地区で契約栽培の出西生姜で秋に採れる古根のみを使用。
店主の来間 久さんにお話をうかがいました。家業を継ぐ前はIT関係にお勤めだったとか。今はお母様と二人で生姜糖を作っているそうです。
これが創業300年の生姜糖です。板チョコ状で、ぽきんぽきんと折って食べるわけです。原材料は砂糖、出西生姜。上白糖が手に入る前はどうしていたのか興味があったのですが、よくわからないそうです。黒砂糖や、和三盆では生姜の風味があわないとか。
製造現場を見せてもらいました。
これが出西生姜です。どことなくワイルド。
「出西生姜は繊維が非常に小さくて完全に溶解する上に独特の甘みと芳香とを失わぬ」と、島根民藝録/出雲新風土記に記載あり。
生姜糖の作り方は「生姜の絞り汁に砂糖を加えて煮つめ、型に入れて固める」。煮つめすぎるとカラメル状になり、時間が足りないと固まらずで、タイミングが難しいとか。この鍋はその肝心な煮つめるとき用の鍋! 年代ものの銅製。もちろん現役!
型も銅製。味があります。ほんとに板チョコみたい。
写真は出西窯のお店のお休み処です。コーヒーやお茶が好きな器でいただけます。来間さんちの生姜糖もおかれています。
最近はパラフィン紙に、ひとつひとつ包まれた個別包装タイプが人気あり。その昔は板チョコ状のものしかなかったそうですが、出西窯の多々納さんにアドバイスを受け、個別包装で出したところ売れるようになったそうです。確かにこの時代、あの板チョコ1枚は持て余すでしょう。
個別パッケージのミニ箱は、六本木ミッドタウン内のディーン&デルーカでも発見しました。クラシックラベルがいい感じです。
出西窯は、浜田庄司や河井寛次郎、バーナード・リーチに教えを請うた民藝窯。「世の中はなにもかも“おかげさま”によるもので、自分の手柄などどこにもない」という無自性の理念をつらぬき、共同作業による器作りをつづけています。
お休み処で出されていた番茶。出雲地方で番茶といえば、これ!です。香ばしくてほんのり甘く、やさしい味わい。
季節限定「生姜の砂糖漬け」。新生姜をうす〜くスライスし、砂糖漬けにした一品で、見た目よりもかなりスパイシー。出西生姜のいい辛みがガツンと伝わり、砂糖の甘みが気になりません。シングルモルトに合いそうな大人の味です。10月から3月までの季節限定商品でホームページから通信販売で購入できます。これはディーン&デルーカにも売っていませんよ!
宮崎県日南油津/杉村本店
December 3, 2007うおぉ〜。 かっこいい!
先日、宮崎県に行きました。でも、トホホの日帰り。慌ただしい移動の車中から見つけたのは木造3階建てのシブイ店舗。 降りて近づくと、ご主人さんが店の前を清掃中。
「写真撮らせてください〜」
「はい、どうぞ」
杉村本店! 金物屋さんです。 工具や塗装用品、セメントの文字も見えます。
「店内もどうぞ見てください」
感じのいいご主人さんの案内で中をのぞかせていただきました。
博物館といいましょうか、現役の資料館!ですね。ロング丈の火鉢も素敵!
おやこれは、焼き印です。
「昔は農業の道具に押したもんですよ。宿の下駄にも使われましたね」そうか、昔は道具も下駄も木製品。焼き印で自分の目印をつけたんですね。
もちろん、販売もしています。1文字1000円。2文字2000円。
「山本」「山」「洋」の字はないか探しましたが、戦後すぐの商品とのことですでに売り切れ。
「今作るとね、この文字の味が出ないんですよ」
お宝探しよろしく探したら「赤」と「菊」を発見!「赤」は、赤峰勝人さんにプレゼントするつもり。
杉村本店は、宮崎県日南市油津1丁目にあります。
昭和7年の建築で2〜3階はお住まい。2階には10以上の部屋と中庭があるそうです。戦時中には軍への供出で外壁の銅板をとられ、戦火で3階の一部を焦がしたことも。平成2年「宮崎県建築百景」に選ばれたそうです。
焼き印は残っているものはごくわずか。ご興味ある人は現地へgo!杉村本店から歩いて30秒のところに文化庁登録文化財の”油津赤レンガ館”もあり、散策する面白さいっぱい。次回、宮崎に行くチャンスがあったら泊まりでいこうっと。
ガイアの野菜も冬景色
November 24, 2007急に冷え込んできました。ダウンコートのお世話になる季節の到来です。代々木上原のガイアさんに行ったら、野菜が冬顔になっていました。
冬といえば根菜類!
葉菜類も負けてはいません。白菜、小松菜はこれからが本番! どれもおいしそう!何つくるかなあ。いい素材をみると迷います。今晩は鍋かなあ〜。
そうだ、かぼちゃもおいしくなりますね。これは「雪娘」さん。その名の通り白い肌。
私たちも冬支度!のガイアスタッフ。左からウズちゃん、トビちゃん、コバちゃん。トビちゃんは結婚してマダムシブヤとなったばかり!おめでとう。
今回、ガイアから連れ帰ってきたひとつが、小川由紀子さん作のルッコラ。この時季のルッコラなんて??ですが、あまりの立派さにどんな味かと興味しんしん。小川さんの作だけあって、葉も厚く、芯もしっかりしています。スーパーのルッコラはどこさわってもふにゃふにゃしてますが。全長30cm以上。隣にれんげを置いてみましたがミニチュアに見えますね。
ルッコラといえばイタリアンですが、鍋の具にすることにしました!
ごまの風味が、鍋の具にぴったり!きのこや油揚げとも相性抜群。しゃきしゃきしておいしい!かむほどに味がじわ〜。風味がいいので薬味も兼ねて!?くれました。さすが小川さん育ちと感心。寒い時期の路地ルッコラは根性あります。
おまけ。ガイア名物のぬか漬け。店長コバちゃんが、満身の力をこめて漬けるぬか漬けです。この季節、赤蕪が入りました。ぬか漬けひとつにも冬を感じますね (^.^)
虎ノ門「W」でSAKE
November 4, 2007「夢酒」森 隆さんが虎ノ門に新しいお店を出されたというので酒販ビジネス館の小島稔さんと行ってきました。虎ノ門駅から3分。この地での日本酒サービス、興味あります。
おぉ、ここだここだ。虎ノ門駅から徒歩3分。新しくできた「東京倶楽部ビル」この奥に[W]はあります。
店内に一歩入ると、中心がキラキラまぶしい。なんと、水があふれているピラミッド状のオブジェが鎮座。「溢れる升のイメージ」なんだとか。ほー。
メニューを見ると、純米大吟醸は”Grand Cru" と書き添えてあります。霞ヶ関界隈はアメリカ大使館も近く、英語圏のお客さまが多いそうです。グランクリュに、味はリッチとかスムースとか表現ワインのごとく。
スタッフ全員SAKEソムリエで「わかりやすい日本酒の説明をこころがけています」
日本酒を飲まない日本人にこそ、このわかりやすさが必要かも。
有楽町国際フォーラム内にある「宝」など話題のお店を次々に手がけてきた森 隆さん。
「ニューヨークでお店を開いたら、こんな感じかな!という店のイメージなんです」
スタイリッシュな空間。森さん、しかし大きい。身長185cm。
いっぱい目は珍しくカクテル系「侍ロック Wーstyle」900円を注文。静岡の開運、本醸造酒にフレッシュかぼす果汁入り。かぼすの酸味が日本酒の甘みをひきたてます。「本醸造のほうがこれにはあいます。本醸造といっても開運のこの品質はさすがです」土井社長、飲んでますよ。
お酒はワイングラスで提供されます。
料理は…とメニューを見ると、グラスで出される日本酒にあう「ここはBARかしらん?」というような、こじゃれたものがいろいろ。間違っても鰯の梅干煮とか、へしことか、ポテトサラダはありません。
まずは「レンコンのアンチョビー炒め」
表面かりっと香ばしく、いい塩け。レンコンはほくほく。おつまみに吉。850円。
そしてこれは、イエローポテトを使ったお料理。周りはバルサミコソース。こじゃれてます。1200円。
こんなおしゃれなら、お燗酒はどんな器で出すんですか? 森さん
「お燗は黒のガラス製でお出しします」
ならば、さっそく”大七の生もと”をお燗で注文。
黒に透明なので、色は見えませんが、そこがまたスタイリッシュ!黒に透明でよく見えない。一緒にいったK島さん、よそ見しながらつぐもんだから、何度もあふれさせてました。「お上品でお願いします」
スタッフは皆さん感じの良さ抜群!お酒の知識も抜群!!
「39.5度でお願いします」
「はい!かしこまりました」
帰りに「升タワー」をじっくり拝見。シャンパンタワーはありますが、日本酒のマスタワーは初めてみました。これで飲めたらまたすごい! 結婚式もいちどしたい(よせ)
上の明かりは月をイメージ。
「世界に発信 Japanese SAKE」なんだそうです。
お酒のラインナップは
●日本酒 開運、大七、田酒、南部美人 、乾坤一、黒龍、〆張鶴、醸し人九平次、東洋美人 他
●焼酎 富乃宝山、佐藤、村尾、百年の孤独、龍宮、長雲、朝日とか
●泡盛 やまかわ、春雨 など
ちょっとおしゃれに日本酒を楽しみたい。素敵な人とゆっくり日本酒で語りあいたい…。日本酒のイメージをよろしく!伝えたい。きゃ〜外国の方を接待しなくちゃ。というときにぴったりなお店です。
○SAKE bistro W
東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング 1階 (銀座線、虎ノ門駅11番出口から3分)
電話03-3501-1811
月〜金ランチ 11〜14(ラストオーダー)ディナー 17〜22:30(ラストオーダー)
土日祝ランチ 11〜14(ラストオーダー)
ディナー 16〜21:30(ラストオーダー)
新丸ビル ムスムス
October 31, 2007東京駅の真ん前!に丸ビルと新丸ビルができてから、丸の内界隈に出かける事が多くなりました。どこからくる人にも便利なので待ち合わせにぴったり。コンランショップ、BEAMS、本、美容院、手ぬぐいまで何でも揃い、何といっても飲食店が莫大に増えたこと!
新丸ビルの7階 ”丸の内ハウス” 統括マネージャーの玉田 泉さんに「ムスムスは食材が面白いですよ。お米は天日干し、野菜や茸など食材は直送です! 社長がこだわってます!」と、教わりました。
じつは「ムスムス」。存在は知っていたのですが、なぜか入ったことがなかったのです。 さっそく玉田さんの案内でランチに行ってきました。ψ(*`ー´)ψ
予想外におばんざいが充実!
わらびと油揚げの煮物、ふきとタケノコの煮物、「ミズ」も出てきました。 無着色のいぶりがっこも添えられてます。
どれも甘すぎず、素材の持ち味を生かした味つけ。おや! おいしいではないですか。東京駅から歩いてこれる店で、このアイテムは貴重。店のインテリアから想像できません〜。
おばんざいをしみじみいただいていると、スタッフがテーブル脇に台を準備。アツアツものが運ばれる気配。
どどどどどど、とスタッフが持ってきてくれたのは、土鍋の炊き込みごはん! ふたを開けると湯気もぉもぉ。ヽ(^。^)丿
秋鮭と秋田県のキノコ名人直送の茸の炊き込みご飯です。天然茸ならではの香りの良さ!味の濃さ! 鮭も甘みがあってふかふか。天日干しのご飯もつやつや、具材の味がしっかりしみて。 お焦げたまりません〜。
「あったかごはんセット」750円。ごはんお代わりOK。この場所で、この素材で、なんという良心的価格。
店はみかけで判断しちゃいけませんね。すみません佐藤社長。
やまよは豚さんが苦手。そのことを伝えると「いい魚が入ってます。それを蒸しましょう!」感じのいいスタッフさん。相談すればいろいろ工夫してくれます。ベジーノも、マクロビーノも相談してみてくださいね。ただし、無理難題はカンベンよ。
店入口のガラスの冷蔵ケースには、野菜がずらり。
卵は生みたて烏骨鶏。
「和食に中華にタイ料理に……と、世界中の料理が食べられる日本ですから「どこの料理を食べるか」ではなくて、「どんな調理法で食べるか」。ナマ、焼く、煮る、いろんな調理法がある中で「蒸す」というスタイルに注目しました!」
と、社長の佐藤としひろさん。
採れたての野菜をさっと蒸して、自然塩をふりかけただけの蒸し野菜サラダ。蒸した白身魚に白髪葱と香菜を乗せて熱々
の胡麻油を回しかけた清蒸鮮魚。ドイツ風に丸ごと蒸し
た大きなジャガイモ……。
素材の良さを最大限に生かす調理法が「蒸す」 ここに行き着いたそうです。
オープンキッチンを覗くと、高く積み重ねられたセイロ、大鍋からは湯気が立ちのぼり、いい感じです。
おそ〜くまで営業してるので、野菜不足の方、深夜残業おつかれさんの方、遠くへ行くバスにお乗りの方、新鮮な素材をヘルシーに食べたい方、足を運んでアツアツ体験してみませんか?
●無国籍料理 ムスムス
東京都千代田区丸の内1−5−1 新丸の内ビルディング 7F 丸の内ハウス電話 03-5218-5200 不定休(新丸ビルに準ずる) 月〜土11:00〜28:00 日祝11:00〜23:00
昼の湯呑み酒
September 4, 2007素敵なお蕎麦やさんを教えてもらいました。駒ヶ根にある「丸富」さんです。
もとは市内にあった人気店で、満を持して別荘地へ移ったとか。
野草の天ぷらや、そばがきなどそそられるお品書きがずらり。器もセンス良し!
天ぷらは大ぶりの片口の器にダイナミックに盛られてきました。
蕎麦がきも甘くてクリーミィ。大根おろしたっぷり添えられています。
お昼時だったのでお酒はちょっとと思っていたら
お品書きに、なんともそそられる言葉が!
昼の湯呑み酒
ヽ(´-`)ノ はぅ
こぅ、なんというかおおらかな感じをうけますよね。
さあ、ご一緒に
昼の湯呑み酒
ヽ(´-`)ノ はぅ
昼の湯呑み酒
ヽ(´-`)ノ はぅ
信州駒ヶ根 丸富さんで、昼の湯呑み酒
はう はう
そんなことを、ぶつぶつぶつぶつ唱えていたら、
「遠慮せずに呑めばいいじゃないですか」とご同席の方々。
……そうですね。あのえっと、わたし、器が見たいんです。ここのお店の器全部素敵なので、どんな器で昼のお酒がくるのかなって興味があって……と、つぶやきながら、へっへ
「昼の湯呑み酒ひとつください」
じゃ〜〜〜ん
骨太な黒い器でどかんときました。なみなみ入ったこれが昼の湯呑み酒。
それにはやっぱり、蕎麦味噌でしょう。蕎麦味噌もひとーつ。
こんがり焼けて、香りだけでもたまらない〜。
グイッ。
ゴークリ。
きっくー。昼の湯呑み酒。
まわりは誰も呑んどらんがな。やまよ、ひとりおじさんの巻。
もちろん、お蕎麦も最高!
香りあり、甘みあり、こしありの三拍子!
すっきりおしゃれなインテリアも快適、器も味も特Aクラスの丸富さんは
お酒好きの心をよくご存知でした。
なにか理由をつけて呑みたがっている……。
なにか理由が……ほ、し、い。
飲食店を経営するかた、理由です。理由。
さて、丸富さん。
駒ヶ根インターから車で5分くらいです。お店のホームページはありませんが、検索するとたくさんひっかかりますよ。
ジャンクやまよシリーズ その1 たこちゃんのタコ焼き
July 24, 2007「どうしても食べさせたい! おいしいんですよ! たこちゃんのタコ焼きっ」
……ヽ(Д´ ゚)ノ タスケテー
強制連行されたとあるタコ焼き屋さん。ほんまにうまいのかいな。赤色ウン番台の紅生姜入ってるのかなあ…と気乗りせずに店の前。初対面の人には言えません。
「普段はオーガニックなものしか食べないんです」と、すかしたことは (-θ-)ノ
おっちゃん焼いてました。
元気いっぱい、冗談口ずさみながらテケテケくるくる焼いてます。
おんや?
なに? あの茶色い洗面器は
いつのまにかタコ焼きは串にささってる。
うんわ〜〜っ (;゚Д゚)
焼きたてアツアツのタコ焼きをどっぶんつけ込んだ!
タコ泳がしているぅ〜 ヽ(´Д`ヽ)(/´Д`)/
タコ焼きダイビング
できあがりました。
表面しなしな、ジューシィタコ焼き!
一緒に食べた大阪人のM嬢いわく「トッピングが一切ないタコ焼き初めて食べたわ〜。食べたあとの歯のこと考えなくていいんやねえ。こんなタコ焼き初めてやわあ」と感心しきり。
確かに、青のりもかつおぶしもマヨネーズものっていないのは初めて見ました。
温度も下がった串ざしのタコ焼きは確かに食べやすい。ソースのように甘くもない。べたつくものがない。ふむ。
洗面器の中身は醤油出汁。
なんでも「たこちゃん」先代のお父さんが考案したそうです。
店の前には、腰くだけなゆるゆる o┤*´Д`*├o かき氷メニューがありました。
右から2番目の「せんじ」ってなに?
煎茶系かと思いきや
なんと「砂糖水」のことだそうです。
「あれ? そういわへんかなあ」
いわへんで ゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚
地域によってさまざまでしょうが「みぞれ」というのが一般的かと。
やまよ幼少のみぎり都会のゲゲゲの町境港では「ガムシロップ」といっていたかな(ウソでっせ)
「たこちゃん」場所は愛知県瀬戸市内にあり。
市内には2軒あり、ここ「たこちゃん」がおいしいそうです。町の人に「たこちゃん」と聞けばすぐわかるといってました。隣は八百屋さんです。駐車場完備。ベンツのワゴンで行っても余裕しゃくしゃく。
ご当地モノっておもしろい!
すりばち館の加藤明子さん
July 16, 2007ごまをすったり、バジルをすったり、すりばちは大活躍! 大中小いろんなサイズを持っています。
こんなにお世話になっているすりばちですが、作っているところを見たことがありません。そこで、日本のおよそ6割のすりばちを作っているという美濃のマルホン製陶所「すりばち館」を訪ねました。
陶芸家であり、すりばち館の館長である加藤明子さん(美人!)にご案内していただきました。明子さんが手にしているのはマルホン製陶所渾身の作、日本最大のすり鉢! 超ビッグです。
「窯と煙突と木造で出来たすりばちの作業場を、21世紀に残したいと願ってつくったのがこの”すりばち館”です」と明子さん。
古いすり鉢や道具が展示されています。明子さんの作品もあり(左端に置かれた見事な壷、大鉢など)
そして、奥へ進むと広い販売室が。元は「モロ」と呼ばれた窯屋の作業場だったそうです。風情あります。
大きささまざまなすりばちは、浅いのあり、深いのあり、絵柄もいろいろで見応えあります!
ありがたいアドバイスもあり。
明子さんがデザインしたすり鉢各種。
「テーブルにそのまま出せるでしょ」
ううーん (≧ω≦。)
ほんとに素敵なデザインがたくさん。
こんなにたくさんのすりばち、一同に見たことありませんから、もぉ、やまよ興奮状態。ヽ(´ω)ノ ダレカトメテ
「さあ、作業場へどうぞ」
は、はい、はい、はい。
マルホン製陶所は、ここ美濃の地で、明治43年に創業。
伝統の技は今もしっかり生きてます。すり鉢は成型後、職人さんが丁寧にくし目をたてていきます。ここが勝負の見せ所。確実に早くがモットー。
乾燥した後、700度で素焼きします。
その後、釉薬をかけて本窯で1230度の高温で焼成されて、ようやく完成となります。
十草という柄の絵付け中です。
うちに持ち帰ったのは(写真右)片口の茶十草、(写真左)片口の深鉢タイプです。何度見ても、ほれぼれ。
山水画、文字などを呉須絵具で手書きしたものもありました。明子さんいわく「絵柄、大きさともに特注も可能!」だそうです。
うぅ。すりばちを引き出物にしたかった。次回はそうしよう(うそうそ)。
深鉢に煮物を入れてみました。
なんてことない田舎の煮物ですが、すりばちのおかげでどっしり感が出ました。
十草柄にはごまあえを入れました。
炒りごまもスイスイすれて使い勝手抜群!
すりごまに味噌、みりん、豆乳を少々入れてさらにすり、ゆでたインゲンをからめました。茶色のストライプがごまあえに表情を与えるようです。
一生使いますね。明子さん。今度は小さいのを買いにいきます!
〒509-5401 岐阜県土岐市駄知町2321-55
マルホン製陶所 「すりばち館」
開館日 金曜、土曜、日曜のみ(月曜〜木曜は要予約)
開館時間 10〜16時
電話 0572−59−8730
FAX 0572−59−1961
玄米キッシュといえばルヴァン
June 4, 2007石臼挽きの国産小麦で天然酵母で発酵。石窯でじっくり焼くフランスの伝統的なパンを焼いて20年!の「ルヴァン」さん。今までもやまよの本で何回か紹介させてもらった長いおつきあいです。「東京で食べるところを教えてください」とリクエストがあったので改めてご紹介します。
ここの「玄米キッシュ」を食べ、あまりのおいしさに”玄米にめざめた”人も多いんです。サクッとしたパイ生地に包まれた、ふっくらモチモチの玄米ごはん。イタリアンテイストかつ、和風要素ありで、すんごいボリューム。満足感いっぱい。ロングセラー商品ですね。
あれば即get!の「野菜のピザ」。旬で野菜が変わります。この日はキャベツ! 香ばしい生地の上にトマトソース、そして柔らかなキャベツがたっぷりトッピング。カリッ、サクッ、ジュワのおいしさ。ルヴァンのパンは隣のcafe 「ル・シャレ」で食べられます。
どうせ行くならパンが充実している午前中がおすすめ。
「ル・シャレ」店内の黒板には本日のメニューが。黒板下のバスケットには焼きたてパンがずらずらずら。石窯から出たばかり。時差のないルヴァンのパンは、最高においしいです。
カフェの名物が、この「サンドイッチプレート」。
ふんわか、もっちりパン各種に、切り干し大根や車麩の煮物など、和風のお総菜がてんこ盛りで動物性食材は不使用。チーズはありなしの注文ができます。ビーガン、マクロビアンHappyなひと皿です。
こちらも変わらぬ人気メニュー「きのこと野菜のスープ」です。
昆布と椎茸のだしに、きのこいろいろ、野菜も各種入ります。仕上げはEXオリーブオイル。やさしい味です。ルヴァンのパンにぴったり。
ジャム、バター、はちみつ、ごまみそペースト、オリーブオイルは+50円でつけることができます。ごまみそペーストはスタンダードアイテム。
店主の甲田幹夫さん。ミッキースマイル!で登場。著書『ルヴァンの天然酵母のパン』(柴田書店刊)はパン作りのバイブル。故郷、長野県上田にもお店があります。
「国産の小麦、ライ麦を自家製粉しています。粉の味が特徴のルヴァンのパンは、野菜やねりごま、醤油や味噌味の和総菜が合うことをカフェで提案しています」
飲み物は、そば茶、野草茶などもあり。みんなにやさしい「ル・シャレ」の名の通り、山小屋みたいなパン・カフェです。
*朝はそりゃもう、目の回るような忙しさ。石窯フル活動! きびきび働くスタッフたち。
店内ではパンのほか、イタリア食材、ワインなども販売しています。
●ルヴァン富ヶ谷店
東京都渋谷区富ヶ谷2-43-13
TEL/FAX 03-3468-9669
8:00〜19:30
日・祭日〜18:00
水曜・第2木曜定休
ル・シャレの営業時間は10〜18:30(日曜祝日は〜17時)
小田急線代々木八幡駅徒歩5〜6分
●ルヴァン信州上田店
長野県上田市中央4-7-31
TEL/FAX 0268-26-3866
7:00〜19:00
水曜・第3木曜定休
営業時間は変更される場合もあります。お出かけ前に確認を。
からほり通りのこんぶ 土居さん「日本一のだしのとり方教室」開催
May 18, 2007
「心地いい暮らしがしたい 素食がおいしい。vol.4」で昆布のイロハを教えていただいた大阪のからほり通り商店街にある、老舗の昆布やさん「こんぶ 土居」。
なんと、だしのとり方教室を始めたのだとか。人数は6名(2名ひと組で3組限定)。受講料は230円(なぜ、230円かには深い意味が)。先生は土居純一さん(独身!)と、お父さんの成吉さん。
日本一の昆布、正真正銘の天然の真昆布です。しかも特級クラスの川汲浜のもの。葉肉も厚く、幅も広い最高級品。色もややあめ色がかったほんまもん。上品なうまみと甘みがあり、澄んだだしがとれるという品です。
昆布の力を最大限に発揮させるために大事なことは
「昆布は乾物。かならず水でしっかりもどしてください。真価が発揮できません。2時間。できればひと晩もどすと最高のだしがとれます」
せっかくのいい昆布でも、力を出しきらなければモッタイナイ! 昆布は乾物だってこと、改めて肝に命じるの巻。
こんぶ 土居的「日本一のだしのとり方」
昆布+鰹節のスタンダードなだし
水 1リットル
真昆布10〜15g
鰹節(昆布と同量)
自然塩2〜3g
ひと晩つけてぷっくりもどった真昆布を、つけた水ごと弱火にかけます。沸騰したら火を止めて昆布を取り出します。
「いい昆布なら少しくらい煮立てても大丈夫です」
取り出すと、こんなに大きくなっています。ビッグショック。「あとで佃煮にしてください」 はい!
このあと鰹節を入れ2〜3分おいてすばやく網でこします。温度が下がった分、もう一度火にかけ、塩を2〜3g加えます。
「はい、完了です」
出来ました。なんと早い。日本一のだしなのに、あっというま!
「フランス料理だとこうはいきませんね(笑)」
きれいに澄んだ出来たてのだし! 美しい〜。
さて、試飲。
つーぃ。おぉ、すこぶるうま味が濃い。濃すぎるほどです。じつは、塩を入れる前にも試飲しましたが、塩不要というくらい味充分でした。ですが、塩を入れて飲んだら、これまたピシリとしまって完璧。
さっそくお椀に注ぎます。
「いいだしなら、具は三つ葉や麩くらいがいいですね」と純一さん。
「和食の1万円のコースに出されるだしと同じですよ。いや、それ以上のコースなのかもしれません(笑)」と成吉さん。
「好みですが、醤油を香りづけ程度に1〜2滴落とすと、味が丸くまとまります」
ぽと、ぽとり。つーぃ。 おぉおおぉ。本当です。
こんぶ土居さんからのone point*
「品質の良い昆布や鰹節なら、温度や抽出時間にあまり神経質になる必要はありません。もし、雑味の出やすい原料を使用する場合は、少し低めの抽出温度にすることですっきりとした味のだしがひけます」
店内にはありとあらゆる昆布で一杯。真昆布の種類もさまざま。日本橋の高島屋でも買えますが、本店でしか買えないレアなアイテム多し。
細切りしおふき、刻み昆布、こんぶあめなどオリジナル製品も数多く、目移りしてしまいます。中でも25年ほど前に作ったという人気の品が「帆立と昆布の 柱こんぶ」。
北海道南茅部産の天然真昆布と天日干し天然帆立貝柱を、醤油、酒、みりんで味つけた逸品です。最近、類似品が出たそうです。
「内容を真似してくれるならいいんですけど」と残念そうな成吉さん。
アミノ酸や酵母エキスなどで人工的に味つけした食品が多いことに危機感をもっている土居さん。それぞれの商品のパッケージに詳しい原材料と、ものによっては割合まで事細かく紹介されています。
「真似してもらえたらええと思って」
えっ!? !Σ(▼□▼メ)
柱こんぶの袋を見てびっくり仰天
「醤油17.6g(大豆・小麦・塩)、昆布16g(道南産天然真昆布)・帆立貝柱8g・酒4.3g(米・米麹)・みりん4.3g(もち米・米麹・米しょうちゅう) 内容量40g
ここまで書いてある商品なんて見たことありません。
さて、230円の講習料のナゾを聞くと
「使った昆布と鰹節と塩の実費です」 なんとっ!! (^^)b
230円あれば、最高級のだし1リットルがとれるという意味なのだそうです。そんな手軽な贅沢!してみたいですね。昆布さえもどしてあれば、あっというま。スタバのコーヒーより安い日本一のだし。おうちでゆっくり味わってみませんか?
・「こんぶ 土居」さん料理雑誌「四季の味」夏号(6月発売)で紹介されるそうです。要チェック!
●こんぶ 土居
大阪市中央区谷町7−6−38
電話06-6761-3914
FAX06-6761-7154
*谷町六丁目駅 4番出口を右に進み、からほり商店街を入って左側にあります。
営業時間 9:00〜18:00
日曜祝日定休 夏期、年始休み